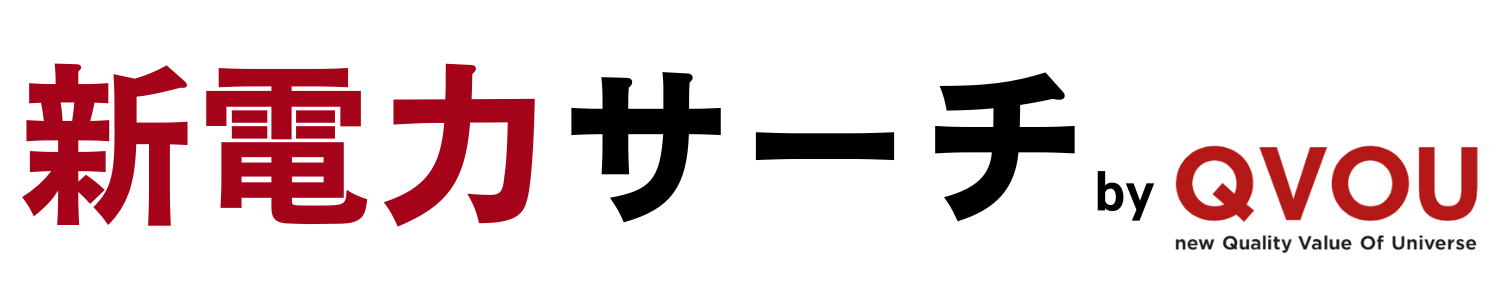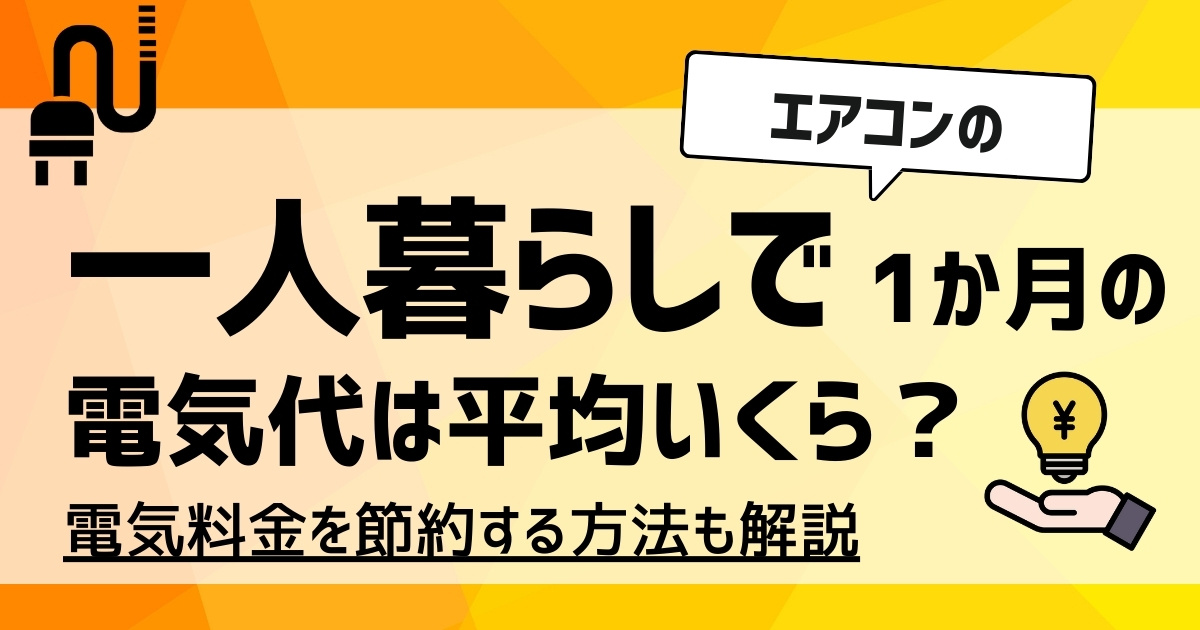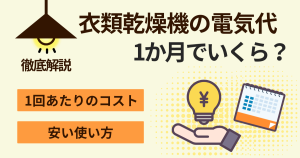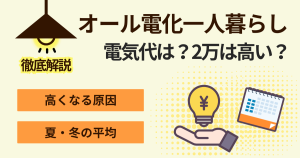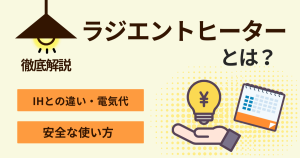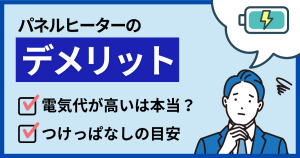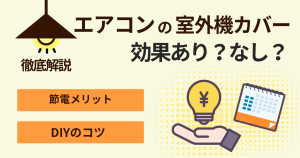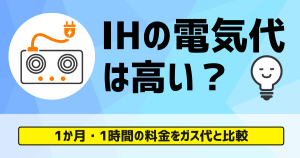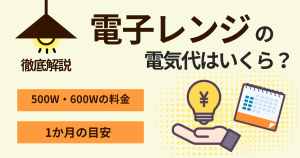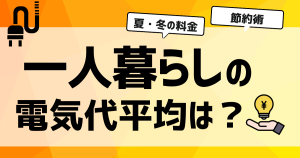エアコンは、夏の暑さや冬の寒さを乗り越えるために欠かせない家電です。
しかし、一人暮らしの場合、電気代を誰かと分担できないため、昨今の電気代高騰が家計に大きな負担となっているかもしれません。
エアコンのスイッチを入れる際に、電気代の不安が頭をよぎる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、一人暮らしにおけるエアコンの1か月の電気代平均額を解説したうえで、すぐに実践できる電気料金の節約方法も紹介します。
エアコンをつけたいものの電気代が心配な方や、ほかの一人暮らし世帯の電気代事情について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
| サービス | サービスの特徴 | 電気料金シミュレーション | おすすめな方 |
|---|---|---|---|
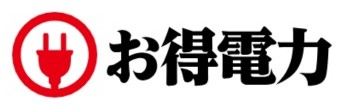 詳細を見る | ・大手電力会社からの乗り換えなら今のプランのまま電気代が確実に安くなる ・乗り換えはスマホで簡単・工事も不要 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ お得電力 従量電灯Bプラン 年間 約8,553円 お得! | ・手間やプラン変更なく電気代を安くしたい方 ・今の電力会社に不満はないが節約はしたい方 |
詳細を見る | ・電気の市場価格に合わせて料金が変動 ・使う時間を工夫すれば 電気代を大幅に節約可能 | 【例:4人家族の場合】 Loopでんき スマートタイムONE(電灯) 月額 約11,119円 ▼ 市場電力(電灯)プラン 年間 約3,180円 お得! | ・ゲーム感覚で積極的に節電を楽しみたい方 ・電気を使う時間を調整できるライフスタイルの方 |
 詳細を見る | ・契約するだけで 「のむシリカ」がもらえる ・電気を使えば使うほどもらえる特典が増量 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ のむシリカ電⼒ 従量電灯Bプラン 年間 約2,844円 お得! | ・電気代の節約と一緒に 健康にも気を配りたい方 ・毎月の電気使用量が 多い家庭 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まず
一人暮らしでエアコンにかかる1か月の電気代はいくら?
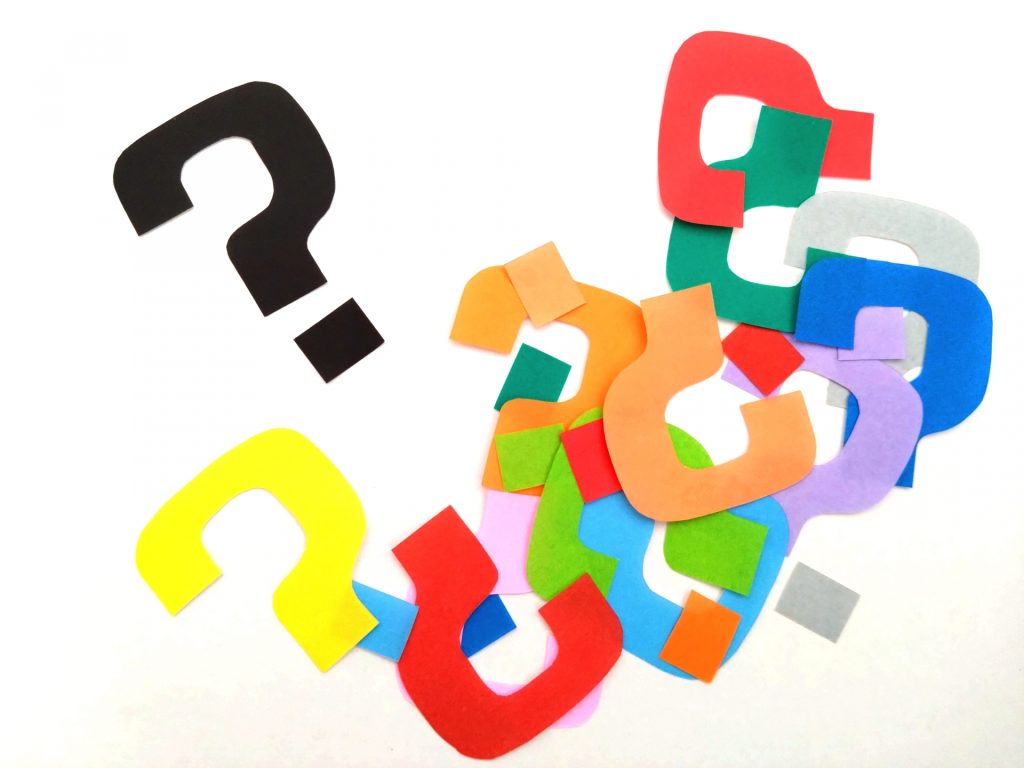
一人暮らしのエアコンにかかる1か月の電気代は、さまざまな要因により大きく変動します。
電気代に影響を与える主な要因は、エアコンの種類や性能、ライフスタイル、季節、居住地域などです。
自宅のエアコンの電気代が高いのか、それとも安いのか気になる方は、まず平均額をチェックしましょう。
ここからは、一人暮らしにおける月々の電気代の平均を紹介します。
月々の電気代の平均
総務省統計局の「家計調査」によると、過去6年における単身世帯の電気代の平均月額は次のとおりです。
| 年度 | 平均月額 |
|---|---|
| 2019年 | 5,700円 |
| 2020年 | 5,791円 |
| 2021年 | 5,482円 |
| 2022年 | 6,808円 |
| 2023年 | 6,726円 |
| 2024年 | 6,756円 |
2019年~2021年の期間を見ると、単身世帯の平均電気代は月5,000円台で比較的安定していました。
しかし、2022年以降は平均月額が6,000円台後半に達しており、電気代は数年で急激に上昇していることがわかります。
電気代の平均月額を季節別に見ると、冬の時期にあたる2024年1~3月は7,150円、夏の時期にあたる2024年7~9月は6,771円です。
一方、春季にあたる2024年4~6月の平均月額は5,839円であり、冬季や夏季と比べると安い結果となりました。
世帯人数に限らず、電気代は季節により大きく変動する点も理解しておきましょう。
エアコンにかかる電気代の平均
経済産業省の資源エネルギー庁によると、家庭における家電製品の1日の電力消費割合のうち、エアコンが占めるのは冬季で32.7%、夏季で34.2%です。
上記の割合と季節別の平均月額を考慮すると、一人暮らしにおけるエアコンの1か月の電気代平均額は次のようになります。
- 冬季:7,150×32.7%=2,338.05円
- 夏季:6,771×34.2%=2,315.682円
上記のとおり、冬季と夏季の平均月額に大きな差はありません。
しかし、実際の電気代はエアコンの種類や性能、使用時間などにより大きく変動します。
平均額はあくまでも目安としてとらえ、自身の使用状況に合わせて毎月の電気代を管理しましょう。
毎日の節約、お疲れ様です!
でも、もっと根本的に電気代を安くしませんか?
一番カンタンで効果が高いのは、今のライフスタイルに合った電力会社を選ぶこと!
電気代の仕組みと内訳

電気代は、大きく分けて次の要素から構成されています。
- 基本料金
- 電力量料金
- 燃料費調整額
・再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)
「基本料金」+「電力量料金」+「燃料費調整額」+「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の合計が、毎月の電気代となります。
電気代の計算は複雑に見えますが、基本的な仕組みを理解すれば、自身でも簡単に算出可能です。
ここからは、電気代の仕組みと内訳について詳しく解説します。
基本料金
電気料金における基本料金とは、電気の使用量にかかわらず、毎月一定額を支払う必要がある料金体系です。
基本料金は、主に「アンペア制」と「最低料金制」の2つに分類されます。
- アンペア制:契約したアンペア数に応じて基本料金が変動する仕組み
- 最低料金制:あらかじめ設定された最低料金が適用される仕組み
アンペア制の場合、契約アンペア数が大きくなるほど、基本料金も高額になる点が特徴です。
契約アンペア数と基本料金は比例関係にあるため、必要以上に高いアンペア数で契約すると、無駄な基本料金を支払うことになりかねません。
一方、最低料金制は従量料金制とも呼ばれ、各契約に対して最低料金が設定されています。
実際に使用した電力量が最低料金に満たない場合でも、設定された最低料金の支払いが必須です。
また、最低料金でカバーされる電力量を超過した場合には、超過分が電気料金として加算されます。
電力量料金
電力量料金とは、電気の使用量に応じて発生する料金です。
計算式は「電力量料金単価(円/kWh)×使用量(kWh)」で、使用した電力量(kWh)に、電力会社が定める料金単価を掛けることで算出可能です。
一般的に電力量料金は、使用電力量が増えるほど高くなります。
多くの電力会社では、使用電力量に応じて料金単価が変動する「段階制料金」を採用しています。
段階制料金は、使用量が少ないほど料金単価が安くなり、使用量が増えるほど料金単価が高くなる仕組みです。
電力使用量の少ない家庭への配慮や、電力需要のピークを抑制する目的で導入されています。
電力量料金は、基本料金と並んで電気料金の主要な構成要素であり、日々の節電努力により削減が期待できるでしょう。
燃料費調整額
燃料費調整額とは、発電に必要な燃料(原油、LNG、石炭など)の価格変動に応じて、毎月自動的に調整される料金です。
燃料価格が上昇すれば燃料費調整額はプラスとなり、電気料金に加算されます。
反対に燃料価格が下落すると燃料費調整額はマイナスとなり、電気料金から差し引かれる点が特徴です。
なお燃料価格は、国際情勢や為替レートなど、さまざまな外部要因により変動します。
燃料費調整額は、外部要因による電気料金の変動をタイムリーに反映させるための仕組みです。
燃料費調整額の算定方法や上限値は、電力会社ごとに異なることから、契約前は燃料費調整額についても確認しておきましょう。
再エネ賦課金
電気料金の一部には、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)も含まれています。
再エネ賦課金とは、風力発電や地熱発電、水力発電などの再生可能エネルギーの普及を促進するための費用です。
再エネ賦課金の単価は国の政策に基づいて毎年見直され、全国一律に適用されます。電力会社ごとに異なるものではありません。
賦課金単価は各年で異なることから、負担する金額が多い年もあれば少ない年もあります。
なお再エネ賦課金は、電気料金の明細に必ず記載されているため、気になる方は一度確認してみるとよいでしょう。
一人暮らしで1か月の電気代が高くなる原因

一般的に電気の使用量が少ない一人暮らしでも、ライフスタイルや料金プランなどにより、電気代が高くなることがあります。
電気代の高騰を招いている主な原因は、次のとおりです。
- 在宅時間が長い
- 料金プランが適切でない
- 部屋が広いまたは多い
ここからは、一人暮らしで1か月の電気代が高くなる原因について詳しく解説します。
効率的に節約するためにも、まずは電気代が高い原因を特定しましょう。
在宅時間が長い
在宅時間が長いことは、一人暮らしで毎月の電気代が高くなる原因の一つに考えられます。
日中家にいる時間が長くなると、照明やエアコン、パソコン、テレビなどの家電の使用時間が必然的に増加します。
とくにエアコンは消費電力が高く、使用時間も長くなりやすいため、電気代を大きく押し上げる要因になります。
在宅時間の長さにより冷蔵庫の開閉回数や調理家電の使用頻度が増えることも、電気代が高くなる原因です。
近年、働き方の多様化やライフスタイルの変化により、在宅時間が増加傾向にあるため、電気代への影響は軽視できません。
可能であれば在宅勤務の日数を調整して、自宅にいる時間を減らす工夫も必要です。
料金プランが適切でない
毎月の電気代が高すぎると感じる場合、料金プランが適切でない可能性があります。
たとえば、夜型の生活をしているにもかかわらず、夜間の料金単価が割高なプランを契約していると、毎月の電気代は高くなる一方です。
夜型の方は夜間の電気代が安くなるプラン、反対に日中の在宅が多い方は昼間の電気代が安くなるプランをおすすめします。
また、契約アンペア数にも注意が必要です。一人暮らしの場合、契約アンペア数が大きすぎると基本料金が高くなり、無駄なコストが発生するかもしれません。
基本料金を抑えるためには、電気の使用量に合わせて契約アンペア数を決めることが大切です。
自身のライフスタイルや電気使用状況に合わせたプランを選び、無理なく電気代を節約しましょう。
部屋が広い・部屋数が多い
一人暮らし向けの賃貸物件は、ワンルームや1Kが一般的ですが、なかには広めの1LDKや2部屋以上ある物件に住んでいる方もいるでしょう。
部屋が広い、もしくは部屋数が多いと、電気代が高くなりやすいため注意が必要です。
部屋数が多い場合、各部屋に照明器具やエアコンなどを設置する必要があり、結果的に消費電力が増加して電気代も高くなります。
また広い部屋には、大型の家電製品を設置することが多いです。
大型の家電製品は消費電力も大きい傾向にあり、さらに電気代が高くなることが予想されます。
部屋の広さや数による電気代高騰を抑えるためには、省エネ性能の高いエアコンや照明器具などの導入が効果的です。
一人暮らしでエアコンの電気代を節約する方法

エアコンは、部屋の温度を大きく変化させる必要があるため、ほかの家電に比べて消費電力が大きいです。
使用時間も長くなりやすいことから、毎月の電気代を上げる大きな原因になります。
そのため、エアコンの使い方を工夫すると、効率的な家計の節約につながるでしょう。
ここからは、エアコンの電気代の節約法を「共通編」「冷房編」「暖房編」に分けて解説します。
共通編
冷房、暖房に共通して有効な節約術は次のとおりです。
- 1日に何度もつけたり消したりしない
- 設定温度を度々変えない
- 自動運転モードの活用
- 定期的なフィルターの清掃
エアコンは起動時に多くの電力を消費するため、1日に何度もつけたり消したりすると、電気代の高騰を招く可能性があります。
そのため、1時間以内の短時間の外出であれば、つけっぱなしがおすすめです。
また、エアコンの使用時は自動運転モードを活用しましょう。
自動運転で一気に室温を設定温度に近づけることで、トータルの消費電力が抑えられ、結果的に電気代の節約につながります。
冷房編
冷房の場合の節約術を紹介します。
- 室温は28℃を目安に設定
- 扇風機やサーキュレーターの併用
- 遮光カーテンやすだれの使用
エアコンは、外気温との差が大きいほど電気代がかかります。そのため、設定温度は低くしすぎず、28℃を目安に設定しましょう。
また、扇風機やサーキュレーターの活用もおすすめです。
室内の空気が回るようになると、冷気の循環がよくなり、必要以上に設定温度を下げずに済むでしょう。
暖房編
暖房の場合の節約術は次のとおりです。
- 設定温度は20℃を目安に
- 厚手のカーテンや断熱シートの使用
- 加湿器の併用
冬場は、厚手のカーテンや断熱シートを使用し、窓からの冷気を遮断しましょう。冷たい空気が部屋に侵入しにくくなると、暖房効率が高まります。
また、暖房を使用する際は加湿器をつけるのもおすすめです。
室内の湿度を上げることで体感温度が高まり、暖かく感じやすくなるため、無駄に暖房の設定温度を上げずに済みます。
一人暮らしで電気代をさらに抑える節約術

一人暮らしで電気代をさらに抑えたい方は、エアコンの使い方を見直すのみでなく、ほかの節約術も実践しましょう。
効果的な節約術として挙げられるのは、主に次の4つです。
- 契約アンペア数を下げる
- 家電の使用方法を見直す
- 省エネ家電に買い替える
- 電力会社を変更する
上記の節約術を組み合わせることで、一人暮らしでも大幅な電気代削減が可能になるかもしれません。
ここからは、それぞれの節約方法について詳しく解説します。日々の生活の中で、意識して取り組んでみてください。
契約アンペア数を下げる
契約アンペア数とは、電力会社と契約している「同時に使用できる電気の量」のことです。
アンペア数が大きいほど同時に使用できる電気量は多くなる一方で、基本料金も比例して高くなる傾向にあります。
契約アンペア数を見直し、必要に応じてアンペア数を下げることで、毎月の基本料金の節約が可能です。
なお、一人暮らしの方の場合、アンペア数は20A~30Aが一般的とされています。
一人暮らしでも高いアンペア数が必要になる場合もありますが、一つの目安として参考にしてみてください。
家電の使用方法を見直す
電気代を節約するためには、家電の使用方法を見直すことも重要です。
具体的な節約方法を家電別に紹介します。
| 家電 | 見直し部分 |
|---|---|
| エアコン | ・設定温度の見直し ・自動運転モードの活用 ・定期的なフィルター清掃 |
| 冷蔵庫 | ・開閉時間の短縮 ・食品を詰めすぎない |
| 照明 | ・LED照明への交換 ・こまめな消灯 ・日中の使用を控える |
| テレビやパソコン | ・エネモードの活用 ・こまめな電源オフ ・画面の明るさ調整 |
| 洗濯機 | ・まとめ洗い ・お風呂の残り湯の活用 |
電気代を効果的に節約したい方は、ぜひ上記の方法を実践してみましょう。
省エネ家電に買い替える
電気代を無理なく節約する方法として、省エネ家電への買い替えも挙げられます。
最新の省エネ家電は、従来の家電に比べて消費電力が大幅に削減されているため、電気代の削減に効果的です。
とくにエアコンや冷蔵庫、テレビなどの大型家電は多くの電力を消費するため、省エネモード搭載の家電に買い替えることをおすすめします。
しかし、省エネ家電は従来の家電に比べて、高額な傾向にあります。
省エネ家電を購入する際は、現在使用している家電の使用年数や、経済的に購入可能かどうかを確認しましょう。
電力会社を変更する
2016年の電力自由化により、消費者はライフスタイルや電気使用量にあわせて、自由に電力会社や料金プランを選択できるようになりました。
基本料金や電力量料金を割安に設定したプラン、時間帯別料金プラン、ポイント還元プランなど、多くの電力会社がさまざまな料金プランを提供しています。
毎月の電気代で悩んでいる方は、電力会社や料金プランを見直すことで、電気料金を大幅に削減できる可能性があります。
電力会社のWebサイトや比較サイトなどを活用し、自身の電気使用量やライフスタイルに適した電力会社を選びましょう。
電気代が気になる方におすすめの新電力会社3選

一人暮らしで電気代を節約する方法として、電力会社の切り替えもおすすめです。
電力会社やプランを見直すことで、電気代の大幅な削減も夢ではありません。
電力会社の切り替えを考えている方には、次の新電力会社がおすすめです。
- お得電力
- 市場電力
- のむシリカ電力
ここからは、それぞれの新電力会社について詳しく紹介します。
自身のライフスタイルや電気の使用状況に合わせて、最適な電力会社を見つけましょう。
お得電力
お得電力は、地域に根差した料金設定とプランを強みとする、新しい電力サービスです。
小規模な設備運営により、管理や人件費などのコストを抑えることで、地域の大手電力会社と比較して、より経済的な料金体系を実現しています。
また、お得電力では、各地域の大手電力会社と同等の多様なプランを提供している点も特徴の一つです。
現在、大手電力会社と契約中の方は、お得電力に乗り換えることで現在と同等のプランを維持しつつ、電気料金の節約ができます。
さらに、契約中の電力会社への連絡、工事の実施、電気機器の交換などの煩雑な手続きは、原則として必要ありません。
切り替えの手続きがネックに感じている方、毎月の電気料金で悩んでいる方は、お得電力がおすすめです。
市場電力
市場連動型の料金体系を採用する「市場電力」は、電力市場の価格変動に応じて電気料金が変動する新電力サービスです。
電気料金は市場価格に連動するため、電力使用の工夫次第で、月々の電気代を賢く節約できる可能性があります。
また市場電力は、切り替え工事や電気機器の交換、契約中の電力会社への連絡などが原則として必要ありません。
切り替え手続きは最短5分で完了するため、仕事や家事で忙しい方でも安心です。
賢く節電に取り組みたい方、切り替え手続きの手間を少しでも省きたい方は、市場電力を検討してみてください。
のむシリカ電力
のむシリカ電力は、霧島天然水「のむシリカ」を販売する運営会社が提供する新しい電力サービスです。
のむシリカ電力に申し込むと、初回契約特典として霧島天然水「のむシリカ(500ml×24本)」が1箱プレゼントされます。
さらに契約更新時にも電気料金に応じて特典が提供され、日々の健康維持にも役立つでしょう。
また、のむシリカ電力は各地域の大手電力会社と比較して、電気料金が割安に設定されている点も魅力です。
電気料金と毎日の飲料水の購入費用をまとめて節約したい方、日頃から飲用する水の品質にこだわりたい方には、のむシリカ電力がおすすめです。
あなたの電気代、どれだけ安くなる?
東京電力から「お得電力」に乗り換えた場合の節約額をチェック!
東京電力の月額料金
お得電力なら…
年間でこれだけお得に!
約2,665円節約
東京電力の月額料金
お得電力なら…
年間でこれだけお得に!
約4,811円節約
東京電力の月額料金
お得電力なら…
年間でこれだけお得に!
約8,553円節約
お得電力を詳しく見る
一人暮らしの電気代に関するよくある質問

最後に、一人暮らしの電気代に関するよくある質問を3つ紹介します。
エアコンの使い方や地域ごとの電気代、水道光熱費の平均などが気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
エアコンはつけっぱなしがよい?
エアコンは起動時に多くの電力を消費するため、基本は「つけっぱなし」にして1日の起動回数を減らす方が、電気代は安くなります。
反対にこまめに消したり、つけたりを繰り返していると、起動のたびに多くの電力を消費し、電気代の高騰を招く点に注意が必要です。
そのため、30分~1時間程度の短時間での外出であれば、エアコンは消さない方がよいでしょう。
ただし、2時間や3時間などの1時間以上の外出の場合、一度エアコンは消すことをおすすめします。
何時間も外出しているにもかかわらず、エアコンの電源がついていると、電気の無駄遣いになります。
とくに夏季や冬季は電気代が高くなりやすいため、少しでも節約できるように、エアコンの使い方を意識してみてください。
地域で電気代の平均は異なる?
一人暮らしの電気代は、地域ごとでも異なります。
2024年における、単身世帯の地域別平均電気代は次のとおりです。
| 地域 | 平均額 |
|---|---|
| 北海道、東北地方 | 7,500円 |
| 関東地方 | 6,566円 |
| 北陸、東海地方 | 6,794円 |
| 近畿地方 | 6,648円 |
| 中国、四国地方 | 7,437円 |
| 九州、沖縄地方 | 6,274円 |
地域別の平均電気代を見ると、北海道と東北地方が最も高い結果となりました。
中国地方と四国地方も比較的高く、寒い地域や暑い地域は冷暖房で多くの電力を消費する分、電気代が高くなりがちです。
一方、人口が集中している関東地方や近畿地方は、ほかの地域に比べて電気代が安い傾向にあります。
一人暮らしの水道光熱費の平均は?
2024年における、単身世帯の水道光熱費の平均額は次のとおりです。
| 平均額 | |
|---|---|
| 電気代 | 6,756円 |
| ガス代 | 3,056円 |
| 水道代 | 2,282円 |
| ほかの光熱費 | 721円 |
| 合計 | 12,815円 |
水道光熱費の中で、とくに高くなりやすいのは電気代です。
夏場のエアコンや冬場の暖房器具の使用は、電気代を大きく押し上げる要因となります。
在宅ワーカーの方であれば、自宅で電気を使用する時間が必然的に長くなるため、より電気代が高くなることが予想されます。
効率的に家計全体の節約に取り組みたい方は、電力会社や料金プランを見直し、電気代の削減を図りましょう。
まとめ

本記事では、一人暮らしにおけるエアコンの1か月の電気代平均額を紹介しました。
エアコンの電気代は、エアコンの種類や性能、生活リズム、季節、居住地域により大きく変動します。
一般的に一人暮らしは、世帯人数が多い家庭に比べて電気代が安い傾向にあるものの、ライフスタイルや料金プラン次第では高くなります。
毎月の電気代を少しでも抑えたい方は、日々の生活の中で積極的に節電に取り組みましょう。
一人暮らしで電気代を節約する方法として、電力会社やプランの見直しも欠かせないポイントです。
電力会社の変更を考えている方は、本記事で紹介した3社の中から選んでみてください。
「高い電気代」は、もう終わりにしませんか?
面倒な手続きは一切不要!Webで完結する電力会社の乗り換えで、今日から賢く節約生活を始めましょう。
今のプランのまま
シンプルに安くしたい
ゲーム感覚で
節約を楽しみたい
電気+αの
嬉しい特典が欲しい
<参考>