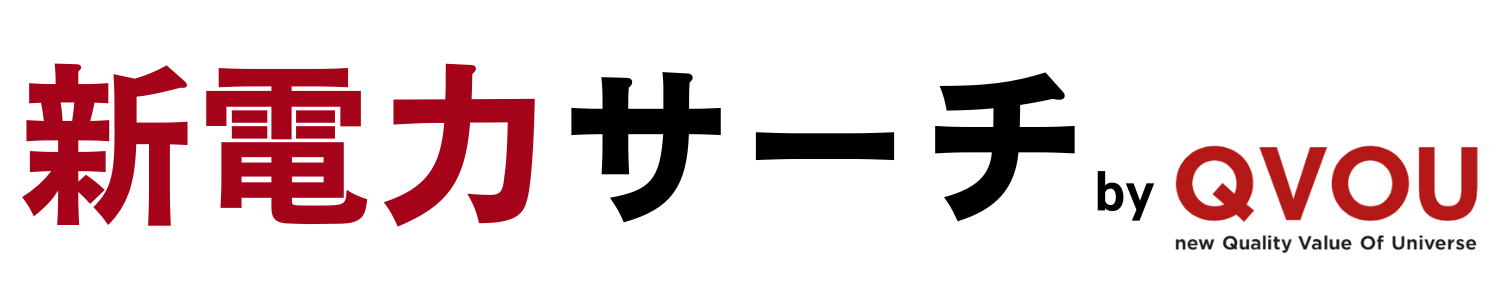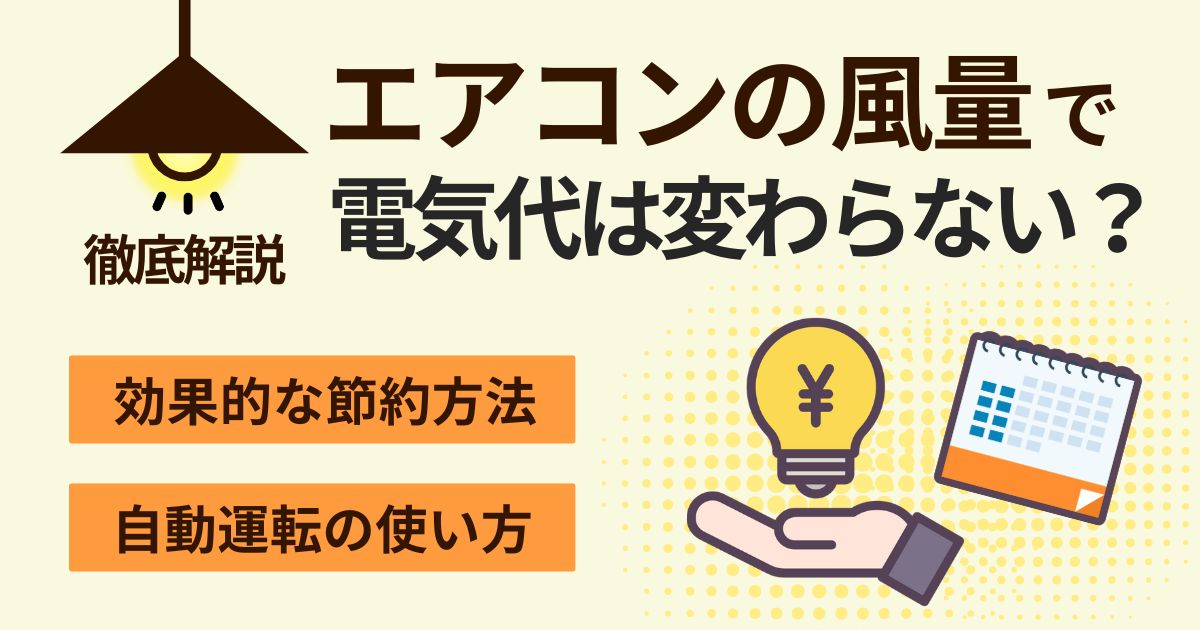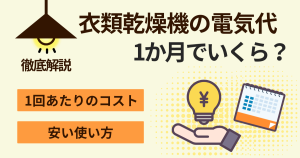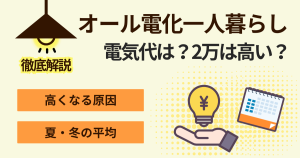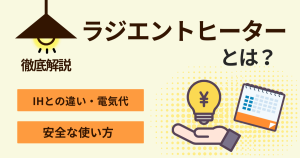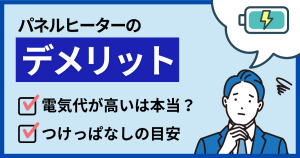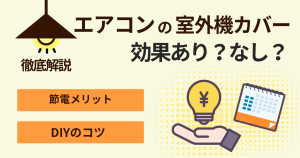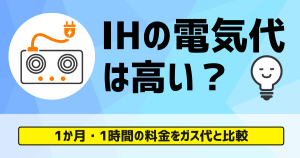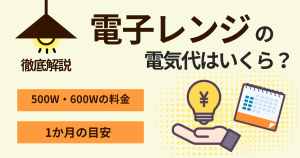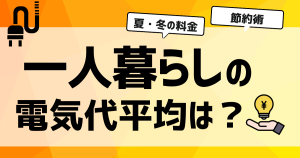「エアコンの電気代を節約したい場合、風量は弱と自動、どちらがよいのか」「風量を変えても電気代は変わらないのだろうか」など、エアコンの賢い使い方を知りたいと考えている方は多いでしょう。
結論からいうと、エアコンの風量を変更しても電気代への影響はごくわずかです。
本記事では、なぜ風量で電気代がほぼ変わらないのか、その仕組みをわかりやすく解説します。
さらに、節電に最も効果的な自動運転の使い方や、電気代を根本から見直す方法まで紹介します。
【結論】エアコンの風量を変えても電気代はほぼ変わらない

風量を変更しても、電気代が大きく変わることはありません。
節約のポイントは、風量ではなく、エアコンの心臓部であるコンプレッサーの稼働をいかに効率的に抑えるかにあります。
ここでは、エアコンの電気代が決まる仕組みと、風量の影響が少ない理由を詳しく解説します。
エアコン電気代の大部分はコンプレッサー
エアコンの消費電力のうち、約8割を占めるのは室外機に搭載されているコンプレッサーです。
コンプレッサーは、圧縮機とも呼ばれ、室内の熱を屋外に排出したり、屋外の熱を室内に取り込んだりする、エアコンで最も重要な役割を担います。
コンプレッサーが稼働する時間の長さが、電気代の大部分を決めることになります。
そのため、節電を考えるうえでは、コンプレッサーの稼働時間をいかに短くするかが最も重要なポイントです。
風量調整が電気代に与える影響はごくわずか
エアコンの風量を調整するファンモーターの消費電力は風量を「弱」から「強」に変更しても、電気代全体への影響はほぼありません。
たとえば、1日8時間エアコンを使用した場合、風量を「弱」から「強」に変えても1か月の電気代の差は100円未満との試算結果もあります。
電気代を気にして風量を弱めるよりも、快適な風量で過ごす方が、結果的に満足度は高くなるでしょう。
弱運転が逆効果になる理由
節約のために設定した「弱」運転が、実は逆効果になることがあります。
風量が弱いと、部屋が設定温度に到達するまでに、エアコンの心臓部であるコンプレッサーが長時間にわたり稼働し続けます。
これにより、トータルの消費電力量が増加し、むしろ電気代が高くなる可能性があるでしょう。
効率的な節約を目指す場合は、短時間で室温を調整し、コンプレッサーの運転時間を短くしましょう。
【節約の正解】エアコンの最も賢い使い方は「自動運転」

エアコンの電気代を賢く節約するための答えは、自動運転にあります。
自動運転は、部屋の状況を判断し、最も効率的な方法で快適な室温を保つため、無駄な電力消費を抑えられます。
ここでは、自動運転がなぜ節電につながるのか、そして他の節約術と組み合わせる方法について解説します。
自動運転が最も効率的に節電できる仕組み
エアコンの自動運転は、最も効率的に節電できる運転モードです。
理由は、センサーが室温を検知し、設定温度に達するまで最適な風量で運転するからです。
運転開始時はパワフルな強風で一気に部屋を快適な温度に調整し、設定温度に達したあとは、自動で微風や送風に切り替わり温度を維持します。
メリハリのある運転により、電力消費の大きいコンプレッサーの稼働時間を最短に抑えられるでしょう。
賢い機能を活用する方法が、節約への近道といえます。
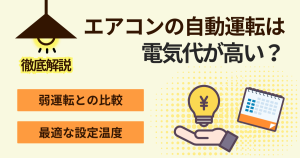
設定温度を1℃変える前に風量で体感温度を調整
エアコンの電気代に最も大きな影響を与えるのは、風量ではなく設定温度です。
設定温度を1℃変えるだけで、消費電力は冷房時は約13%、暖房時は約10%も変わるといわれています。
そのため、少し暑さや寒さを感じたときに、すぐにリモコンで設定温度を操作するのは得策ではありません。
まずは風量を調整してみましょう。風量を強くすれば体感温度は下がり、暖房時には風向きを下げることで足元が暖かく感じられます。
一工夫で、快適さを保ちながら、効果的に電気代を節約できるでしょう。
参照:環境省「家庭部門のCO2排出実態統計調査 家庭のエネルギー事情を知る」
すぐにできる!合わせ技でさらに節約効果アップ
自動運転とあわせて実践したい、効果的な節約術は次の3つです。
- フィルター掃除は2週間に1回が目安
- 室外機の周りはスッキリと
- サーキュレーターや扇風機で空気の循環を促す
フィルターにホコリが詰まると、空気の通り道が塞がれてエアコンの効率が著しく低下します。
無駄な電力消費の原因となるため、2週間に1回を目安にフィルターを掃除しましょう。
室外機の吹き出し口の周りに物を置いたり、カバーで覆ったりすると、熱交換の効率が悪くなり、消費電力が増加します。
室外機の周りは常に整理整頓し、風通しをよくしておくとよいでしょう。
サーキュレーターなどを併用して部屋の空気をかき混ぜることで、室内の温度ムラがなくなります。
これにより、エアコンが効率よく部屋全体を快適な温度に保てるようになり、無駄な運転を減らすことができます。
日々の節約術には限界も!根本的な見直しを検討しよう

エアコンの自動運転やフィルター掃除など、日々の節約術は大切です。
しかし、「なぜか電気代があまり安くならない」と感じることはありませんか。
原因として考えられるのは、毎月の電気代の大部分を占める、電気料金プランそのものにある可能性があります。
ここでは、日々の工夫だけでは電気代が下がりにくい理由と、その根本的な解決策について解説します。
節約をしても電気代が下がらない根本原因
エアコンの運転方法を工夫しても、電気代の削減効果には限界があります。根本的な原因は、契約している電気料金プランにあるかもしれません。
たとえば、毎月固定でかかる基本料金や、電気1kWhあたりの電力量料金単価が割高なプランを契約している場合、いくら使用量を減らす努力をしても電気代は安くなりません。
日々の節約とあわせて、契約内容そのものに目を向けることが、効果的なコスト削減につながります。
電気料金の内訳を知ることが見直しの第一歩
毎月の電気料金は、主に次の項目で構成されています。
- 契約アンペアにより決定する基本料金
- 使用量に応じて変動する電力量料金
- 燃料価格の変動に合わせて調整する燃料費調整額
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金
とくに電力会社の料金設定が大きく異なるのは、「基本料金」と「電力量料金」です。
そのため、「基本料金」と「電力量料金」の安いプランに切り替えることが、電気代を根本から見直すための重要な鍵となります。
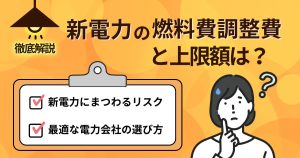
最も効果的な節約は電力会社の乗り換え
これまで紹介した節約術も有効ですが、より根本的かつ効果的に電気代を削減したい場合、電力会社の契約を見直すことをおすすめします。
2016年4月からはじまった電力自由化により、自身のライフスタイルに合った電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。
これにより、多くの事業者が競争力のある価格や独自のサービスを提供しています。
次の章では、数ある選択肢の中から、とくにおすすめの電力会社「お得電力」を紹介します。
賢く節約するなら「お得電力」への乗り換えがおすすめ
「電気代を根本から見直したいけれども、複雑な手続きやわかりにくい料金プランは避けたい」と考えている方におすすめするのは、新電力サービス「お得電力」です。
お得電力は、現在の生活スタイルを変えることなく、シンプルに電気代の節約を目指せるサービスです。
ここでは、お得電力が多くの方に選ばれている3つの理由について、具体的に解説します。
シンプルでわかりやすい料金体系が魅力
お得電力の最大の魅力は、そのシンプルな料金体系にあります。
現在契約している大手電力会社のプランとサービス内容はほぼそのままで、毎月の基本料金と電力量料金の両方が安くなる仕組みです。
そのため、複雑な料金プランを一つ一つ比較検討する必要がなく、電気の品質や使い勝手が変わる心配もありません。
これまで通りの感覚で電気を使いながら、賢く固定費を削減したいと考える方に最適なサービスといえるでしょう。
具体的な電気代削減額の目安
実際にどのくらい安くなるのか、具体的な削減額を見てみましょう。
お得電力の公式サイトでは、世帯人数に応じた節約額の目安が公開されています。
たとえば、東京電力エリアで契約中の方がお得電力に切り替えた場合、2人から3人世帯では年間で約4,811円、4人から6人世帯では年間で約8,553円の電気代が削減できる可能性があります。
そのため、多くの家庭で明確な節約メリットが期待できるでしょう。
安心で簡単な乗り換え手続き
お得電力への切り替え手続きは、驚くほど簡単でスピーディーです。スマートフォンやパソコンから、最短5分で申し込みが完了します。
面倒な工事は一切不要で、現在契約中の電力会社への解約連絡もお得電力が代行するため、手間がかかりません。
また、運営会社の株式会社Qvouは創業40年の豊富な実績を持つ企業であり、安心して長く利用できる点も大きな魅力です。
エアコンの電気代に関するよくある質問

エアコンの電気代や使い方に関して、多くの方が抱える疑問に回答します。
日々の運転音の対策や、他の運転モードとの違いなど、認識しておくと役立つ情報をまとめました。
暖房を使うときも、風量の考え方は同じですか?
基本的な考え方は冷房のときと同じです。
暖房時も、電気代の大部分を占めるのはコンプレッサーの稼働であり、風量の影響はごくわずかです。
そのため、暖房利用時も自動運転に設定すると効率的です。
暖かい空気は上に溜まりやすいため、風向きをなるべく下に向けると、足元から暖まりやすくなり快適性が増します。
「除湿」や「しずかモード」の電気代はどうですか?
除湿(ドライ)には種類があり、電気代が異なります。
単に室温を少し下げる弱冷房除湿は、通常の冷房との消費電力に大きな差はありません。
しかし、室温を下げずに湿度だけを取る再熱除湿は、一度冷やした空気を温め直すのに多くの電力を消費するため、冷房よりも電気代が高くなる点で注意が必要です。
また、しずかモードは運転音を抑えるためにコンプレッサーの働きを弱めるため、部屋が快適な温度になるまで時間がかかり、むしろ電気代が高くなることがあります。
自動運転なのに寒すぎたり風が弱まらなかったりします
自動運転がうまく機能しない場合、いくつかの原因が考えられます。
まず、部屋の広さに対してエアコンの能力が見合わないケースです。
また、エアコン本体にある室温センサーの周辺環境(直射日光が当たる、家具の裏など)により、室温を正しく検知できていない可能性も考えられます。
窓からの熱の出入りが大きいなど、建物の断熱性が低い場合も、エアコンが効きにくい原因となります。
つけっぱなしとこまめなオンオフの比較
エアコンは、電源を入れてから部屋が設定温度になるまでの間、つまり起動時に最も多くの電力を消費します。
そのため、30分程度の短い時間の外出であれば、こまめに電源をオンオフするよりも、つけっぱなしにしておく方が、トータルの消費電力を抑えられる場合が多いでしょう。
ただし、これは部屋の断熱性能や外の気温など、さまざまな条件により変動します。
長時間の外出の場合は、電源オフにするのを忘れないようにしましょう。
まとめ

本記事では、エアコンの風量と電気代の関係、そして効果的な節約術について解説しました。
エアコンの電気代の大部分はコンプレッサーの運転にかかる消費電力であり、風量よりも自動運転で効率的に稼働を抑えると節約につながります。
日々の工夫も大切ですが、より大きな節約効果を求める場合、電力契約そのものを見直すことをおすすめします。
とくにお得電力は、今の生活を変えずに電気代を安くできる、賢い選択肢の一つです。
今回の知識を活かし、快適さと節約を両立する最適な方法を見つけてください。
<参考>
お得電力