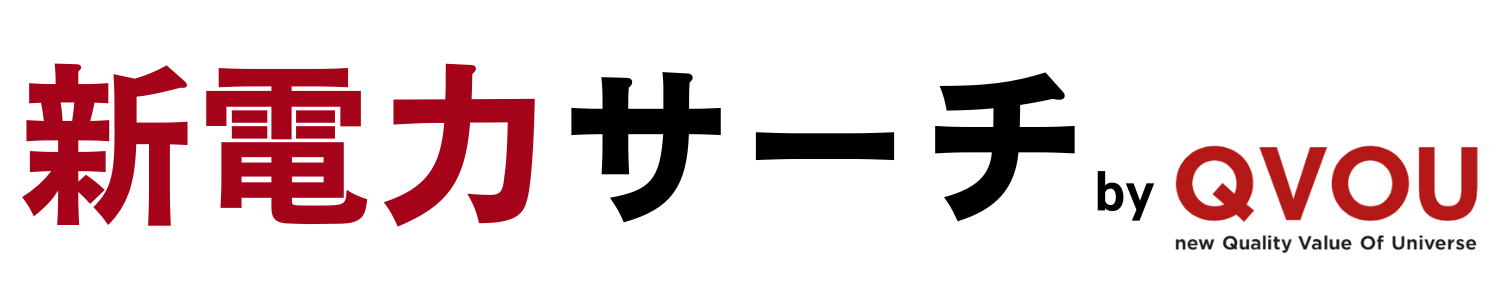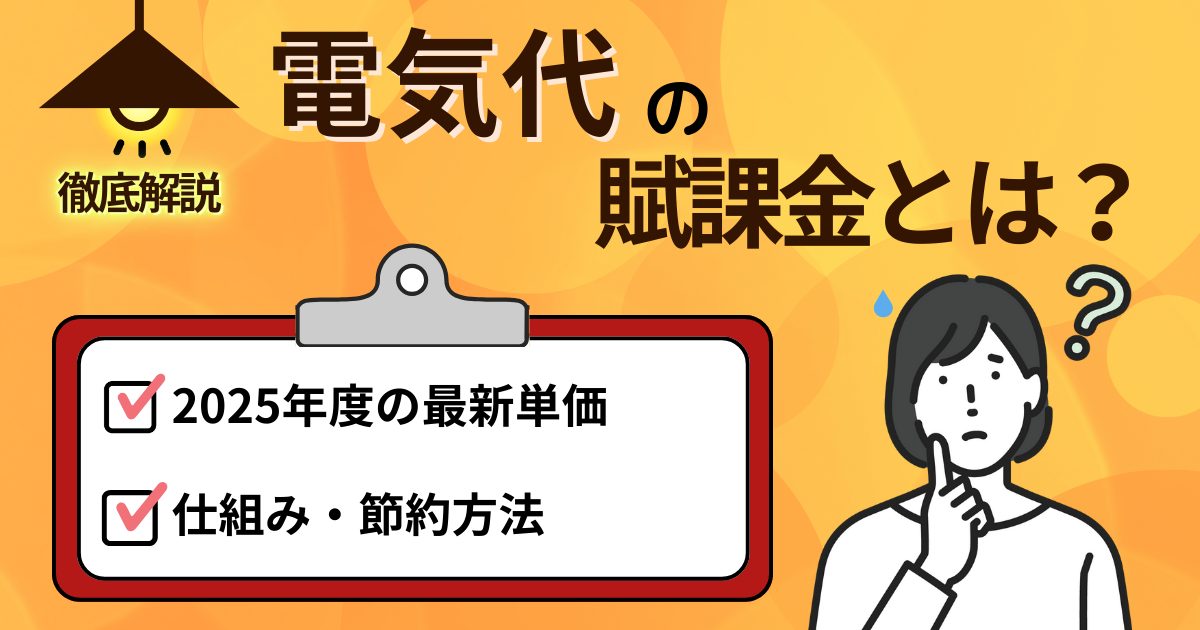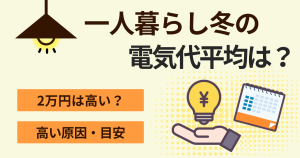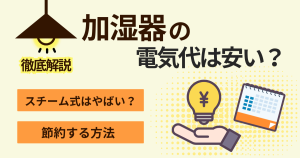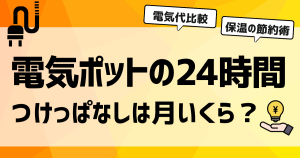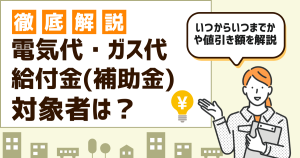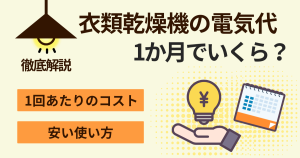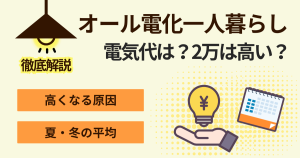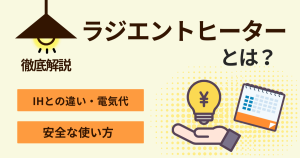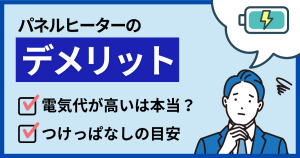毎月の電気料金の明細書は、家計を管理するうえで重要な指標です。
しかし、その中にある再生可能エネルギー発電促進賦課金という項目について、その内容や支払う必要性に疑問を持つ方も少なくありません。
結論として、この賦課金の支払いは避けられませんが、電気代全体の総額を安くする方法はあります。
本記事では、電気代の賦課金とは何か、その仕組みや2025年度の最新単価はいくらかをわかりやすく解説します。
電気代に関する正しい知識を身につけたい方、家計の負担を少しでも減らしたい方は、ぜひ参考にしてください。
【結論】電気代の賦課金とは「再生可能エネルギーを普及させるための国民負担」

電気料金の明細を見て、賦課金という項目に疑問を感じる方もいるでしょう。
この賦課金は、正式には「再生可能エネルギー発電促進賦課金」といい、私たちの生活に欠かせない電気の未来に関わる大切なお金です。
この章では、賦課金に関する基本的な知識を解説します。
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の基本的な意味
- 電気料金明細における賦課金の位置づけと仕組み
- なぜ賦課金制度が必要なのか、その目的と背景
- 「賦課金(ふかきん)」の正しい読み方
ここからは、各項目について詳しく解説します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは?
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを普及させるために、電力会社が買い取る費用を電気利用者全員で負担する制度のことです。
この仕組みは、国が再生可能エネルギーの普及を促すために設けた「固定価格買取制度(FIT制度)」を支えるためにあります。
よく税金と間違われることがありますが、これは税金ではなく、毎月の電気料金に含まれる料金の一部です。
出典:買取価格・期間等|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー
電気料金における賦課金の仕組み
賦課金の金額は、毎月の電気使用量(kWh)に、国が毎年定める賦課金単価を掛け合わせて計算されます。
計算式
電気使用量(kWh)×再エネ賦課金単価
そのため、電気を使えば使うほど、賦課金の負担額も増える仕組みです。
この賦課金単価は、どの電力会社と契約中でも、住んでいるエリアにかかわらず全国一律で同じ金額が適用されます。
なぜ賦課金制度が必要なのか?その目的
この賦課金制度には、主に2つの大きな目的があります。
- 日本のエネルギー自給率を高める
- 地球温暖化対策に貢献
一つは、化石燃料への依存度を下げ、日本のエネルギー自給率を高めることです。
もう一つは、発電時にCO2(二酸化炭素)を排出しないクリーンなエネルギーの割合を増やし、地球温暖化対策に貢献することです。
この制度を通じて、再生可能エネルギー発電設備の導入を社会全体で促進し、持続可能なエネルギー供給体制を構築することを目指しています。
【2025年度最新】再エネ賦課金の単価は1kWhあたり3.98円に決定

毎年変動する再エネ賦課金ですが、2025年度の最新単価が経済産業大臣より発表されました。
ここでは、最新の賦課金単価と、それに伴う家計への影響について解説します。
- 2025年度の最新単価と適用期間
- 標準的な家庭における月々、年間の負担額シミュレーション
- これまでの賦課金単価の推移と今後の見通し
- 賦課金単価が変動(値上げ・値下げ)する理由
それぞれの内容を具体的に解説します。
2025年度の賦課金単価と標準家庭の負担額
2025年度の再エネ賦課金単価は、1kWhあたり3.98円に決定しました。
たとえば、1か月の電気使用量が300kWhの標準的な家庭の場合、月々の負担額は1,194円(税込)、年間にすると14,328円(税込)の負担となります。
家庭の人数別の負担額の目安は、次の表を参考にしてください。
| 世帯人数 | 電気使用量目安 (1か月) | 賦課金負担額目安 (1か月) | 賦課金負担額目安 (年間) |
|---|---|---|---|
| 1人暮らし | 200kWh | 796円 | 9,552円 |
| 2人暮らし | 300kWh | 1,194円 | 14,328円 |
| 3人暮らし | 350kWh | 1,393円 | 16,716円 |
| 4人暮らし | 400kWh | 1,592円 | 19,104円 |
なお、2025年度の賦課金単価は、2025年5月検針分から2026年4月検針分の電気料金に適用されます。
出典:再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価を設定します (METI/経済産業省)
これまでの賦課金単価の推移【グラフで解説】
再エネ賦課金の制度がはじまった2012年度から現在までの単価の推移は、次のグラフの通りです。
出典:資源エネルギー庁の公表データに基づき作成
グラフを見ると、制度開始から単価は上昇し続けてきました。
2023年度に一度単価が引き下げられましたが、これは電力の市場価格が影響した一時的なもので、2024年度以降は再び大幅な値上げとなっています。
今後も、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、負担額は変動していくことが予想されます。
なぜ賦課金単価は毎年変わるのか?
賦課金単価が毎年変動する主な理由は、再生可能エネルギーの買取費用や、電力の卸売市場の価格などが毎年変わるためです。
たとえば、太陽光発電などの導入量が増えれば、電力会社が買い取る電気の量も増え、その分だけ買取費用が増加します。
こうしたさまざまな要因を基に、経済産業大臣が専門家の意見を聞きながら、毎年度の単価を決定しているのです。
賦課金単価は変えられないが、電力会社の切り替えで電気代総額は安くできる

賦課金の負担を少しでも減らしたいと考えるのは自然なことですが、賦課金単価そのものを安くする方法はありません。
しかし、電気代全体で考えれば、総額を安くすることは十分に可能です。その最も効果的な方法が、電力会社の見直しです。
どの電力会社でも賦課金単価は全国一律
はじめに知っておくべき重要な事実は、再エネ賦課金の単価は、法律に基づいて国が定めているため、全国一律であるということです。
これは、大手電力会社と契約していても、新電力に切り替えても変わりません。
電気の使用量が同じであれば、どの電力会社と契約していても、賦課金の請求額は同じになります。
そのため、電力会社を切り替えても賦課金が安くなることはありません。
見直すべきは基本料金と電力量料金
基本料金
契約内容に応じた固定費
電力量料金
電気の使用量に応じた変動費
燃料費調整額
燃料価格の変動を調整
再エネ賦課金
再エネ普及のための費用
電気代の請求額は、主に4つの項目で構成されています。
- 基本料金:契約アンペアなどに応じて毎月固定でかかる料金
- 電力量料金:電気の使用量に応じてかかる料金
- 燃料費調整額:火力発電の燃料費の変動を調整する料金
- 再エネ賦課金:再生可能エネルギーを普及させるための料金
上記4つのうち、どの電力会社でも単価が同じなのは再エネ賦課金のみです。
電力会社によって大きく料金が異なる「基本料金」と「電力量料金」を見直すことこそ、電気代総額を節約するための最も重要な鍵といえるでしょう。
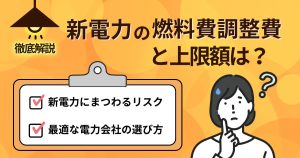
【根本的な解決策】電気代を確実に安くしたいなら「お得電力」がおすすめ
賦課金の負担は避けられませんが、電気代の総額を根本的に見直したいと考えるなら、電力会社の切り替えが最も効果的です。
なかでも、シンプルに安さを実感したい方には「お得電力」がおすすめです。
「お得電力」がなぜおすすめなのか、その理由を具体的に解説します。
- 「お得電力」が大手電力会社より安くなるシンプルな理由
- 世帯人数別、年間節約額シミュレーション
- 切り替えは簡単、電気の品質や安全性は変わらない安心感
ここからは、各項目について詳しく解説します。
大手電力会社のプランより確実に安くなる料金設定
「お得電力」の最大の魅力は、そのわかりやすさにあります。
各エリアの大手電力会社(東京電力や関西電力など)の標準的なプランと比較して、基本料金と電力量料金単価が安く設定されている点が特徴です。
そのため、複雑な条件や期間限定のキャンペーンを気にすることなく、毎月の電気代がシンプルに安くなります。
たとえ賦課金が値上がりしたとしても、それ以上に電気代の基本部分が安くなるため、結果として年間の電気代総額を抑えることにつながります。
【独自試算】世帯別の年間節約額
実際に「お得電力」に切り替えると、年間でどのくらい電気代が安くなるのでしょうか。
東京電力からお得電力に切り替えた場合、次のような節約効果が期待できます。
| 世帯人数 | 試算条件(東京電力) | 年間削減額(約) | 5年間削減額(約) |
|---|---|---|---|
| 1人世帯 | ・従量電灯B・30A・200kWh/月 | 2,665円 | 13,324円 |
| 2~3人世帯 | ・従量電灯B・40A・350kWh/月 | 4,811円 | 24,055円 |
| 4~6人世帯 | ・従量電灯B・50A・600kWh/月 | 8,553円 | 42,766円 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まれていません。
お得電力に切り替えることで、年間数千円から一万円近い固定費を削減できるでしょう。
申し込みは最短5分、電気の品質は今まで通りで安心
電力会社の切り替えと聞くと、「手続きが面倒そう」「電気が不安定にならないか不安」と感じる方もいるでしょう。
しかし「お得電力」なら、申し込みはスマートフォンやパソコンから最短5分で完了します。
切り替えに伴う工事や費用、自宅への訪問なども一切なく、現在契約中の電力会社への解約連絡も不要です。
切り替え後も、居住地域の電力会社が管理する送配電網を使って電気が届けられるため、電気の品質や停電のリスクはこれまでと変わらず、安心して利用できます。
運営会社である株式会社Qvouは創業40年(2025年時点)の歴史を持つ企業であり、サービスの信頼性も魅力です。
電気代の賦課金に関するQ&A

最後に、賦課金に関してよく寄せられる質問に回答します。
- 再エネ賦課金の支払いは義務ですか?
- 再エネ賦課金はいつまで続くのですか?
- 再エネ賦課金が「おかしい」「払いたくない」といわれるのはなぜですか?
- 太陽光発電を設置していても賦課金はかかりますか?
それぞれの質問にわかりやすく回答します。
再エネ賦課金の支払いは義務ですか?
再エネ賦課金は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」という法律に基づいて、電気を契約しているすべての方に支払いが義務付けられています。
そのため、個人の意思で支払いを拒否したり、免除されたりすることは原則としてできません。
再エネ賦課金はいつまで続くのですか?
現時点で、再エネ賦課金制度の明確な終了時期は定められていません。
制度の根幹であるFIT制度(固定価格買取制度)の買取期間が最長で20年間であることから、少なくとも2030年代頃までは継続し、その後も何らかの形で国民負担が続く可能性があると考えられています。
国のエネルギー政策によって将来的に見直される可能性はありますが、当面は長期的な負担が続くでしょう。
出典:買取価格・期間等|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー
再エネ賦課金が「おかしい」「払いたくない」といわれるのはなぜですか?
制度の目的は理解できても、支払いに納得できないと感じる方がいるのも事実です。
再エネ賦課金が「おかしい」「払いたくない」といわれる主な理由として、国民全体の負担によって特定の発電事業者の利益を支える仕組みである点や、制度開始から現在に至るまで負担額が上昇し続けてきた点が挙げられます。
とくに、近年の電気代高騰と相まって、家計への負担が増していることに対する不満の声が大きくなっているといえるでしょう。
太陽光発電を設置していても賦課金はかかりますか?
太陽光発電を設置している家庭でも、電力会社から電気を購入している分については、ほかの家庭と同様に再エネ賦課金が請求されます。
ただし、発電した電気を電力会社に売る「売電」の際には、賦課金は関係しません。
まとめ

本記事では、電気代の再エネ賦課金とは何か、その仕組みや2025年度の最新単価はいくらかについて解説しました。
賦課金は再生可能エネルギーを普及させるための重要な費用であり、単価は全国一律で、支払いも法律上の義務です。
そのため、賦課金自体を安くすることはできませんが、電力会社を切り替えて基本料金や電力量料金を見直すことで、電気代全体の総額を抑えられます。
電気代の見直しについては、専門的知見を持つ当サイトの情報を参考に、家庭に最適な判断をしてください。
根本的な電気代削減に関心のある方は、サービス名「お得電力」で検索し、公式サイトで詳細を確認してみましょう。
参考記事)
水素の力で豊かに生きるための水素健康活用研究所