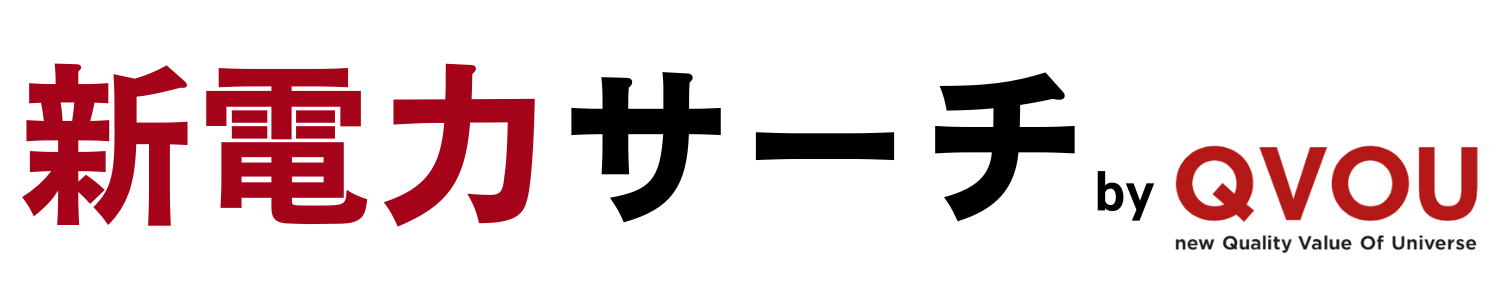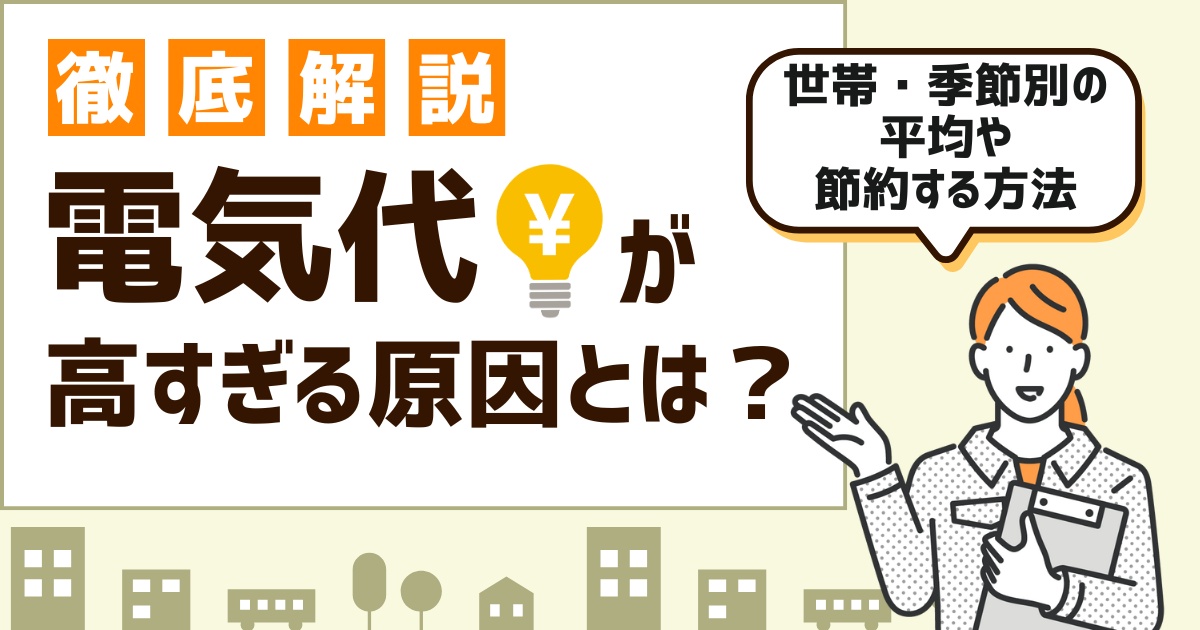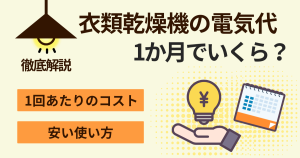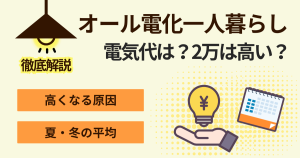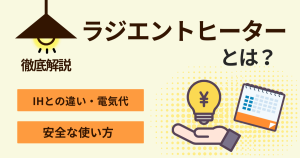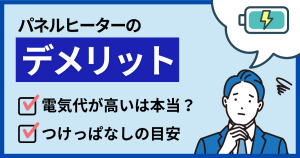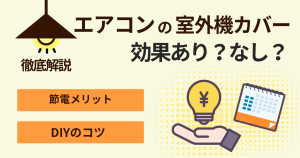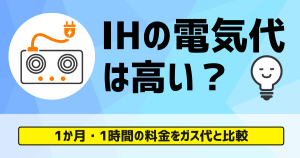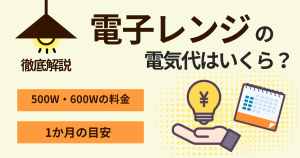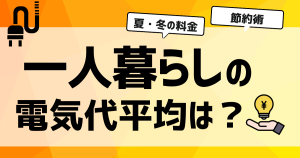近年、電気代の高騰が家計を圧迫しており、多くの方が頭を悩ませています。
とくに夏季や冬季など冷暖房の使用頻度が高まる季節は、電気代が予想以上に跳ね上がり、家計の大きな負担となります。
毎月の請求書を見るたびに「電気代が高すぎる」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、電気代が高くなる原因を徹底的に分析し、世帯別および季節別の平均電気代をもとに、具体的な節約方法を紹介します。
毎月の電気代が高すぎることで悩んでいる方、すぐに実践できる簡単な節約術を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
| ライフスタイル |
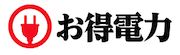
|

|
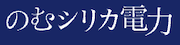
|
|---|---|---|---|
|
ケース1 共働きで 日中不在がち |
\節約期待度/
生活を変えず、確実に節約したい家庭に最適。シンプルに料金が安くなるのが最大のメリットです。 |
\節約期待度/
日中不在時は恩恵が少なめ。電気をよく使う朝晩・休日の価格高騰リスクに注意が必要です。 |
\節約期待度/
大手より安い料金+「のむシリカ」特典が魅力。標準的な使用量でもお得感をプラスできます。 |
|
ケース2 在宅ワーク中心で 昼間によく使う |
\節約期待度/
確実に安くなる安心感が魅力。大きな節約より、安定した割引を求める方におすすめです。 |
\節約期待度/
市場価格が安い昼間に電気を使えるため、電気代を大幅に削減できる可能性が最も高いプランです。 |
\節約期待度/
電気使用量が多い家庭に最適。「のむシリカ」特典を多く受け取れるため、料金+特典でお得です。 |
|
ケース3 家族が多く 電気使用量が多い |
\節約期待度/
使用量が多いほど削減額もアップ。シンプルに電気代を安くしたい家庭に最適です。 |
\節約期待度/
使用量が多いため、市場価格高騰時のリスクが大。時間帯を気にせず使う家庭には不向きです。 |
\節約期待度/
電気料金に応じて「のむシリカ」特典。電気使用量が最も多い家庭で、特典価値が最大になります。 |
そもそも電気代の仕組み・内訳は?

電気料金は、主に次の要素で構成されています。
- 基本料金
- 電力量料金
- 燃料費調整額
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)
毎月の電気代は「基本料金」+「電力量料金」+「燃料費調整額」+「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の合計金額です。
まずは、電気代の仕組みと内訳について解説します。
基本料金
基本料金とは、電気の使用量に左右されず、毎月一定の金額を支払う料金体系のことです。
基本料金は、「アンペア制」と「従来料金制(最低料金制)」の2つに分けられます。
- アンペア制:契約アンペアの大きさに比例して、基本料金が変動する仕組み
- 従来料金制(最低料金制):あらかじめ決定された最低料金が適用される仕組み
アンペア制の場合、契約アンペア数が大きければ大きいほど、基本料金も高くなる傾向があります。
契約アンペア数と基本料金は連動しているため、必要以上のアンペア数で契約をおこなうと、余分な基本料金を支払うことになりかねません。
一方、関西や中国、四国地方、沖縄で採用されている従量料金制では、各契約に対して最低料金が設定されている点が特徴です。
実際の電力使用量が最低料金に満たない場合でも、設定された最低料金の支払いは必須となります。
また、最低料金で賄える電力量を超過した際には、超過分の電力量が電気料金に上乗せされます。
電力量料金
電力量料金は、使用した電力量に応じて発生します。
電力会社が定めた料金単価を、使用した電力量(kWh)に乗じることで算出され、計算式は「使用量(kWh)×電力量料金単価(円/kWh)」です。
一般的に電力量料金は、使用する電力量が増えるほど高くなります。
多くの電力会社では、使用電力量に応じて料金単価が段階的に変わる「段階制料金」を採用しています。
段階制料金は、電力の使用量が少ないほど料金単価が割安となり、電力の使用量が増えるにつれて料金単価が割高になるシステムです。
基本料金とともに電気料金の主要な構成要素である電力量料金は、日々の節電の取り組み次第では、削減が可能です。
燃料費調整額
燃料費調整額とは、燃料価格の変動に応じて毎月調整される金額です。
燃料価格が上がると燃料費調整額はプラスとなり、電気料金に加算される一方で、燃料価格が下がると燃料費調整額はマイナスとなり、電気料金から差し引かれます。
燃料価格は、為替レートや国際情勢など、外部の多岐にわたる要因により変動します。
燃料費調整額は、外部要因に起因する燃料価格の変動をタイムリーに反映させる仕組みです。
燃料費調整額の算定方法や上限値は電力会社ごとに異なるため、契約前は燃料費調整額についても事前に確認しておきましょう。
再エネ賦課金
電気料金の構成要素の一つとして、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)も挙げられます。
再エネ賦課金は、風力発電や太陽光発電、地熱発電、水力発電などの再生可能エネルギーの普及を後押しするための費用です。
再エネ賦課金の単価は国の政策に基づいて毎年見直され、全国一律で適用されるため、電力会社により単価が異なることはありません。
賦課金単価の変動により、負担する金額が大きくなる年もあれば、小さくなる年もあります。
電気料金の明細には、再エネ賦課金が必ず記載されているため、気になる方は一度明細を確認してみてください。
電気代が高すぎる?平均はいくら?
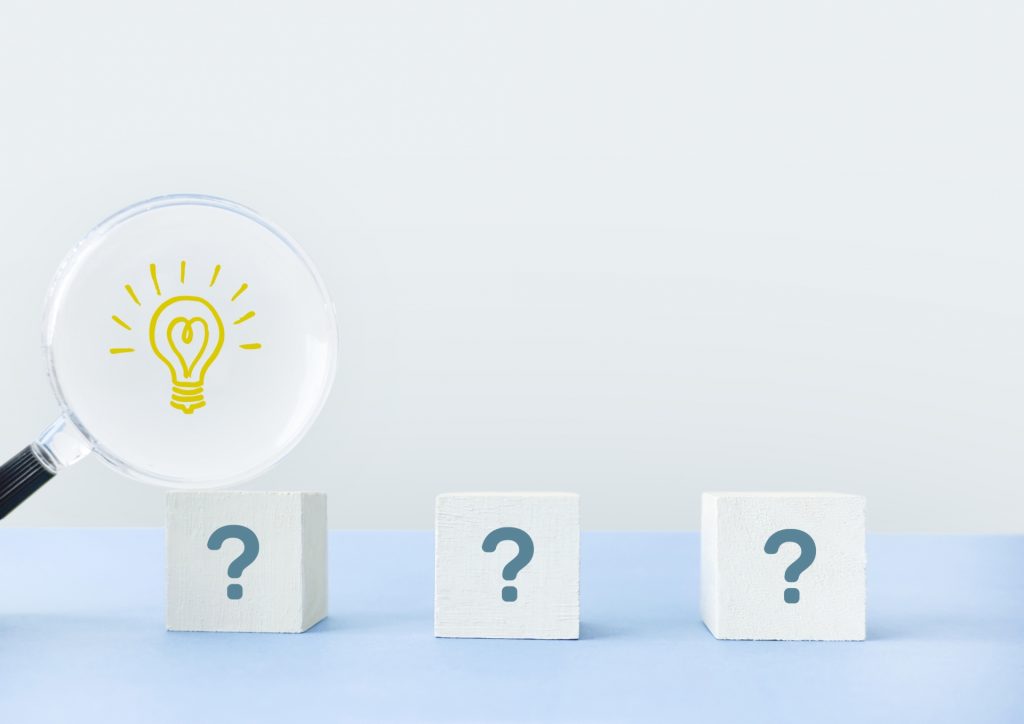
電気代は、世帯人数や季節、地域などにより大きく異なります。
我が家の電気代は高いのか、それとも安いのか気になる方は、平均額をチェックしましょう。
ここからは、電気代の平均を世帯人数と季節に分けて紹介します。
世帯人数別
2024年における、世帯人数別の電気代平均月額は次のとおりです。
| 世帯人数 | 平均月額(2024年) |
|---|---|
| 1人 | 6,756円 |
| 2人 | 10,878円 |
| 3人 | 12,651円 |
| 4人 | 12,805円 |
| 5人 | 14,413円 |
| 6人 | 16,995円 |
基本的に電気代は、世帯人数の多さに比例して高くなる傾向にあります。
とくに1人世帯と2人世帯では差が大きく、月の平均電気代は2人暮らしの方が約4,000円も高いことがわかります。
世帯人数が多いと電気代が高くなる理由は、照明やテレビ、冷蔵庫などの家電製品の使用時間や回数が増えるためです。
また家族一人一人の生活リズムが異なる家庭であれば、常に誰かが電気を使用している状態になり、より電気代が高くなることが予想されるでしょう。
季節別
2024年における、季節別の電気代平均月額は次のとおりです。
夏
| 世帯人数 | 夏の平均月額(2024年7~9月) |
|---|---|
| 1人 | 6,771円 |
| 2人 | 10,732円 |
| 3人 | 12,769円 |
| 4人 | 12,997円 |
| 5人 | 14,143円 |
| 6人 | 16,996円 |
冬
| 世帯人数 | 冬の平均月額(2024年1~3月) |
|---|---|
| 1人 | 7,150円 |
| 2人 | 12,044円 |
| 3人 | 13,761円 |
| 4人 | 14,091円 |
| 5人 | 16,305円 |
| 6人 | 19,971円 |
春・秋
| 世帯人数 | 春の平均月額 (2024年4~6月) | 秋の平均月額 (2024年10~12月) |
|---|---|---|
| 1人 | 5,839円 | 6,356円 |
| 2人 | 10,199円 | 10,535円 |
| 3人 | 11,585円 | 12,486円 |
| 4人 | 11,850円 | 12,282円 |
| 5人 | 13,089円 | 14,112円 |
| 6人 | 15,363円 | 15,650円 |
季節ごとの電気代平均月額を比べると、世帯人数にかかわらず、冬の電気代が高いことがわかります。
夏、冬の電気代が高くなりやすいのは、春、秋よりも外との気温差が大きいためです。
外気温と室内温度の差が大きくなるほど、多くの電力が必要となることから、結果的に電気代が高くなります。
一方、春や秋は比較的過ごしやすい気候のため、冷暖房器具の使用頻度が減る分、冬や夏と比べて電気代が安い傾向にあります。
電気代が高すぎると感じる5つの原因

電気代が高すぎると感じる主な原因には、次のような点が挙げられます。
- 電気料金が値上がりしている
- 電気の使用量が増えた
- 料金プランが適切でない
- 待機電力が多い
- 盗難や漏電
ここからは、電気代が高すぎると感じる原因について解説します。
電気代を少しでも抑えたい方は、まず原因を把握しましょう。
電気料金が値上がりしている
電力会社の料金改定により、電気料金が値上がりしているケースも少なくありません。
料金改定の内容は、基本料金の見直しや電力量料金の単価変更、燃料費調整額の変動など、さまざまです。
とくに燃料価格の高騰は、燃料費調整額を通じて、毎月の電気料金に大きく影響します。
なお電力会社が料金改定をおこなう場合は、公式サイトやメール、マイページなどで必ず案内されるため、常に最新の情報をチェックしておきましょう。
電気の使用量が増えた
急に電気代が高くなった場合は、単純に家庭での電気使用量が増えた可能性もあります。
電気料金は、使用量に応じて加算されるため、使用量が増えれば電気代も高くなります。
たとえば夏季や冬季は、冷暖房器具の使用時間が増えることで、電気代が高くなりがちです。
また在宅勤務やオンライン授業など、ライフスタイルの変化により自宅で過ごす時間が増え、電気代が高くなるケースもあります。
直近で電気代が増えた方は、まず1か月あたりの電気使用量をチェックしてみるとよいでしょう。
料金プランが適切でない
電気代が高すぎる原因として見落とされがちなのは、現在契約中の料金プランが適切でないことです。
電気料金プランは、一人暮らし向けや電気使用量が多い家庭向け、割引や特典が充実したものなど、さまざまな種類があります。
契約しているプランがライフスタイルに適していないと、電気代が高くなることもあります。
在宅勤務が多い、夜間に電気をよく使用するなど、自身のライフスタイルにあわせて最適なプランを選ぶことが大切です。
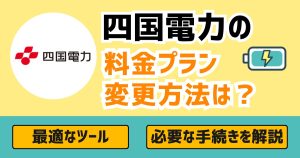
待機電力が多い
待機電力とは、家電製品の電源がオフの場合でも、コンセントにプラグが挿し込まれているのみで消費される電力のことです。
待機電力は、一つ一つの家電製品ではわずかな量ですが、複数の家電製品が常に待機状態にあると、電気代に影響するかもしれません。
経済産業省の調査によると、家庭1世帯あたりの全消費電力量のうち、待機電力は5%以上を占めるとされています。
家電製品の使い方を工夫すれば、待機電力を減らせるかもしれません。
機器のプラグをコンセントから抜いたり、オンオフの切り替えスイッチがついた電源タップを使用したりすれば、年間の待機時消費電力量を約49%削減できるといわれています。
盗難・漏電の可能性がある
電気の使用量が少ないにもかかわらず、電気代が高い場合は、電気が盗難されているかもしれません。
電気の盗難は「盗電」とも呼ばれ、他人が無断で自宅の電気を使用している状態です。
盗電の方法としては、外部コンセントからの無断使用や、配線への不正な接続などが考えられます。
盗電されている疑いがある場合は、屋外に不審な配線や機器がないか、電気メーターの動きを定期的に確認しましょう。
また電気代が高い原因として、漏電も考えられます。通常、漏電が発生するとブレーカーが落ち、漏電し続けることはない仕組みのため、電気代が高くなる原因にはなりません。
しかし、ブレーカー自体が故障している場合、漏電してもブレーカーが落ちないことから、電気代が高くなる可能性があります。
漏電した場合は、すぐに電力会社に問い合わせましょう。
高すぎる電気代を節約する方法

電気代が高すぎると感じる場合、さまざまな節約方法を組み合わせることで効果を期待できます。
電気代の効果的な節約方法は、主に次のとおりです。
- 家電の使い方を工夫
- 省エネ家電への買い替え
- 部屋の断熱性を高める
- 太陽光発電の設置
- 電力会社の切り替え
ここからは、電気代の節約方法について詳しく解説します。
毎月の電気代で悩んでいる方は、日々の生活の中で積極的に取り組んでみてください。
家電の使い方を工夫する
電気代を節約するためには、家電の使い方を見直すことが大切です。
たとえば、エアコンの使用時はサーキュレーターを併用する、冷蔵庫に食品を詰めすぎない、テレビ画面の明るさを調整するなどが挙げられます。
家電の使い方を見直すことで、消費電力の削減につながり、電気代を効果的に削減できます。
省エネ家電に買い換える
省エネ家電への買い替えは、長期的な視点で見ると非常に効率的な対策です。
最新の省エネ家電は、古い家電に比べて消費電力が大幅に削減されており、電気代の節約に大きく貢献します。
とくにエアコンや冷蔵庫など、消費電力の大きい電化製品を省エネ搭載のものに買い替えると、より高い節電効果が得られるでしょう。
長期的な節電効果を求める方は、省エネ家電の導入を検討してみてください。
部屋の断熱性を高める
家電製品のなかでもエアコンは消費電力が高く、使用時間も長くなりやすいため、電気代を高くする要因となります。
エアコンの電気代を抑えたい方は、部屋の断熱性を高めるよう意識しましょう。
部屋の断熱性を高めることで、冷暖房効率が向上し、電気代を大幅に削減できる可能性があります。
部屋の断熱性を高める方法の一例は次のとおりです。
- 窓ガラスに断熱フィルムを貼る
- 厚手のカーテンや断熱カーテンの使用
- 二重窓や複層ガラスへの交換
自身の住環境にあわせて、上記の断熱対策を検討してみてください。
太陽光発電を設置する
太陽光発電とは、太陽光を電気エネルギーに変換する発電方式です。
自宅で発電した電気を自家消費すれば、電力会社から購入する電気量を減らせるため、電気代の削減につながります。
なお、太陽光発電で余った電気は、電力会社に売ることも可能です。
太陽光発電の設置は初期費用がかかるものの、電気代の節約や環境への貢献など多くのメリットがあるため、ぜひ設置を検討してみてください。
電力会社を切り替える
多くの電力会社では、独自の料金プランや割引サービスを提供しています。
電力会社の切り替えをおこなうことで、現在の契約よりも電気代を安くできる可能性があります。
電力会社を切り替える際のポイントは、複数の電力会社の料金プランを比較検討し、自身のライフスタイルに適したプランを選ぶことです。
ライフスタイルに合わないプランを契約すると、電気代が高くなる可能性もあるため、電力会社は慎重に選ぶことをおすすめします。
電気代が高すぎる方におすすめの新電力会社3選

新電力会社は、多様な料金プランやサービスを提供しており、自身のライフスタイルにあわせて選ぶことで、電気代を節約できる可能性があります。
毎月の電気代が高すぎる方には、次の3つの新電力会社がおすすめです。
- お得電力
- 市場電力
- のむシリカ電力
ここからは、それぞれの新電力会社の特徴やおすすめポイントを紹介します。
自身の状況にあわせて比較検討し、最適な電力会社を選んでください。
お得電力
お得電力は、地域密着型の料金プランとサービスが魅力の新電力会社です。
電気の使用量にかかわらず、一人一人のニーズに適した多彩なプランを全国で展開しています。
注目ポイントは、地域の大手電力会社と比較して割安な料金設定です。
お得電力に切り替えると、現在契約中のプランと同等の内容で、電気代の削減ができます。
料金プランの選択肢を重視し、大手電力会社からの切り替えを検討している方には、お得電力がおすすめです。
市場電力
市場電力は、電力市場の価格と連動する料金体系が特徴的な新電力会社です。
市場価格が低い時間帯に電気を多く使用すれば、電気料金を大幅に削減できる可能性があります。
とくに昼間は市場価格が低くなりやすく、日中の電気使用が多い方は、電気代の削減効果を実感しやすいでしょう。
また市場電力は、スマートフォンから最短5分で切り替え手続きが完了する点もメリットです。
電気料金の節約に積極的に取り組みたい方や、切り替え手続きが面倒に感じる方は、市場電力への切り替えを検討してみてください。
のむシリカ電力
のむシリカ電力は、霧島天然水「のむシリカ」との連携がユニークな新電力会社です。
地域ごとの電力需要に合わせた料金プランを準備し、大手電力会社よりもお得な料金設定を目標としています。
また、のむシリカ電力に申し込むと、契約時に水(500ml×24本入り)が1箱、更新時にも電気料金に応じて水がプレゼントされます。
健康に関心がある方には、電気代の節約と健康維持を両立できる魅力的なサービスといえるでしょう。
高すぎる電気代に関するよくある質問
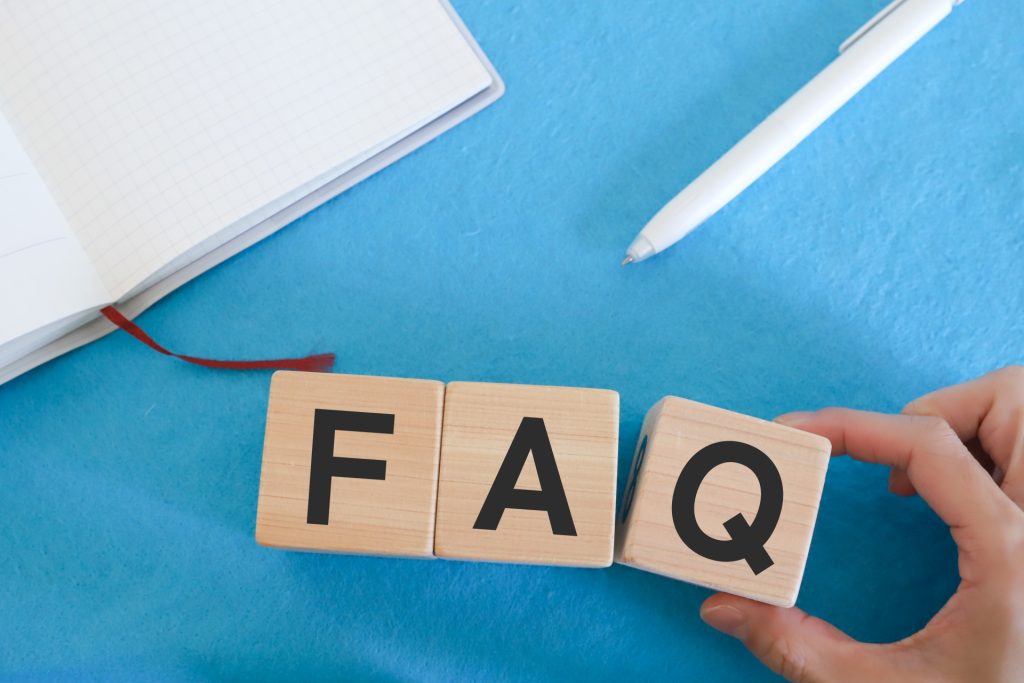
最後に、高すぎる電気代に関するよくある質問を3つ紹介します。
電気代に関して疑問や不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
オール電化は電気代が高い?
オール電化住宅とは、調理や給湯、冷暖房などの熱源をすべて電気でまかなう住宅です。
オール電化を導入した場合、使い方や料金プラン次第では電気代が高くなる可能性があるものの、必ずしも電気代を高騰させる原因になるとは限りません。
次の表で、オール電化住宅と、電気とガス併用住宅の電気代を比較しました。
| 世帯人数 | オール電化住宅 | 電気とガス併用住宅 |
|---|---|---|
| 1人世帯 | 10,777円/月 | 10,805円/月 |
| 2人世帯 | 13,406円/月 | 17,377円/月 |
| 3人世帯 | 14,835円/月 | 19,716円/月 |
| 4人世帯 | 16,533円/月 | 1,9613円/月 |
それぞれの電気代平均月額を比較すると、オール電化住宅は2人世帯以上の方であれば、ガス併用住宅よりも光熱費を抑えられる可能性があります。
一方、1人暮らしの場合は大きな差がないため、オール電化を導入する際はメリットとデメリットを踏まえたうえで、慎重に検討した方がよいでしょう。

今後も電気代は高騰する?
電気代は、今後も値上がりが続いていくと考えられます。
EIA(米国エネルギー省エネルギー情報局)による長期予測では、天然ガスも石炭も2050年まで値上がりが続くと予測されています。
天然ガスと石炭は、火力発電に必要な燃料です。火力発電は日本の電源構成の大半を占めているため、天然ガスと石炭の高騰は、そのまま電気代に反映されます。
なお、火力発電以外の有力な発電方法として「再生可能エネルギー」と「原子力発電」がありますが、コストや不安定性、安全面などの課題から、火力発電への依存は残る見通しです。
今後の電気代の正確な予測は難しいものの、総合的に考慮すると、今後も上昇傾向が続く可能性は高いでしょう。
国からの補助金は終了した?
政府による「電気・ガス料金負担軽減支援事業」は、2026年1月~3月使用分までの3か月間実施されます。
2026年4月以降の支援については発表されておらず、補助金終了後の電気代負担は実質的に増加する見込みです。
まとめ

本記事では、電気代が高くなる原因や平均電気代、効果的な節約方法について解説しました。
電気代が高い原因は、電気料金の値上がりや使用量の増加、自身のライフスタイルにあっていない料金プランなどさまざまです。
月々の電気代を抑えるためには、さまざまな節約方法を組み合わせることが大切です。
家電の使い方を工夫したり、省エネ家電に買い替えたりなど、積極的に節電に取り組むことで、電気代が安くなる可能性があります。
さらに電気代を節約するためには、電力会社の見直しも欠かせません。
本記事で紹介した3社の中から、電気の使用状況やライフスタイルにあわせて、最適な電力会社を選んでみてください。
参考記事)