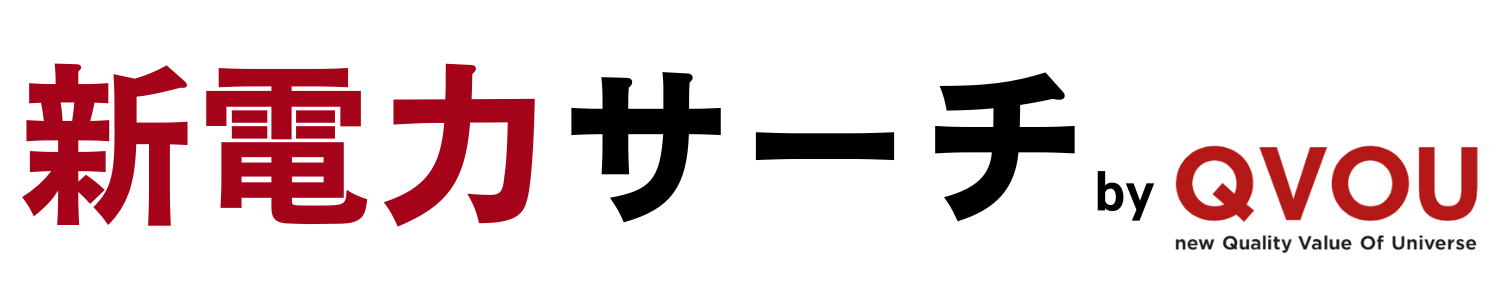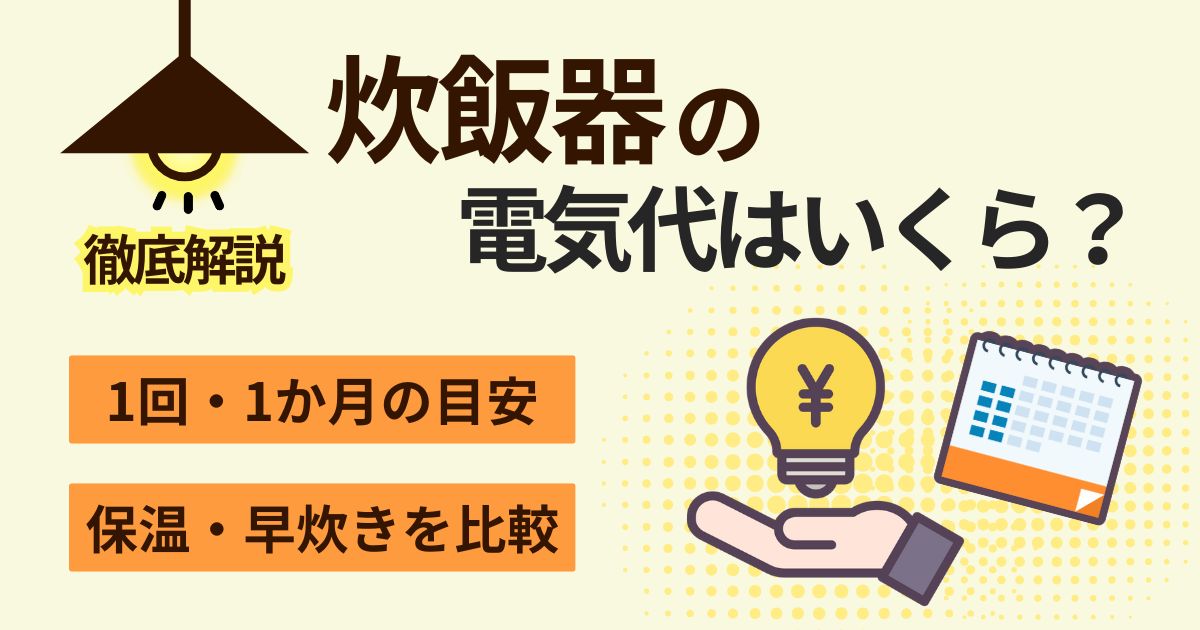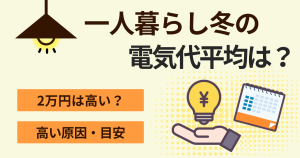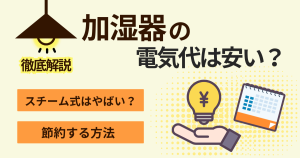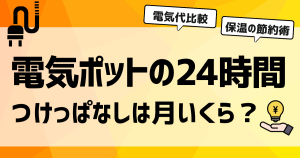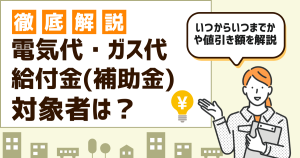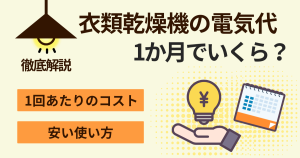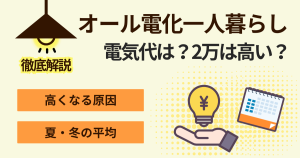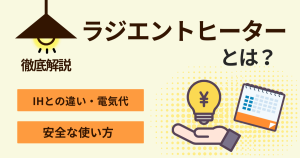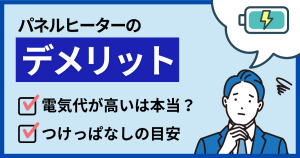毎日使う炊飯器の電気代、実際のところどれくらいかかっているのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
炊飯1回あたりのコストはもちろん、保温機能の電気代や早炊き機能を使った場合の違いなど、具体的な数値や比較情報を知りたいという声もよく聞かれます。
本記事では、炊飯器の電気代に関する基本的な知識から、1回あたり、1か月あたりの具体的な目安、そして保温と早炊きの比較まで詳しく解説します。
炊飯器の電気代に関する疑問を解消し、賢く節約していきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
| サービス | サービスの特徴 | 電気料金シミュレーション | おすすめな方 |
|---|---|---|---|
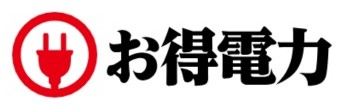 詳細を見る | ・大手電力会社からの乗り換えなら今のプランのまま電気代が確実に安くなる ・乗り換えはスマホで簡単・工事も不要 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ お得電力 従量電灯Bプラン 年間 約8,553円 お得! | ・手間やプラン変更なく電気代を安くしたい方 ・今の電力会社に不満はないが節約はしたい方 |
詳細を見る | ・電気の市場価格に合わせて料金が変動 ・使う時間を工夫すれば 電気代を大幅に節約可能 | 【例:4人家族の場合】 Loopでんき スマートタイムONE(電灯) 月額 約11,119円 ▼ 市場電力(電灯)プラン 年間 約3,180円 お得! | ・ゲーム感覚で積極的に節電を楽しみたい方 ・電気を使う時間を調整できるライフスタイルの方 |
 詳細を見る | ・契約するだけで 「のむシリカ」がもらえる ・電気を使えば使うほどもらえる特典が増量 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ のむシリカ電⼒ 従量電灯Bプラン 年間 約2,844円 お得! | ・電気代の節約と一緒に 健康にも気を配りたい方 ・毎月の電気使用量が 多い家庭 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まず
【結論】炊飯器の電気代は使い方次第!1回・1か月の目安と節約術を徹底解説

毎日使う炊飯器ですが、その電気代が実際いくらかかっているのか、気になる方もいるでしょう。
炊飯器の電気代は、1回の炊飯にかかる費用のみでなく、保温機能の使用時間や早炊き機能の利用など、使い方によって大きく変わります。
ここでは、炊飯器の電気代に関する基本的な情報から、具体的な目安、そして1か月にかかるおおよその費用までを詳しく解説します。
炊飯1回あたりの電気代とその計算方法
炊飯器でご飯を1回炊くのにかかる電気代は、次の計算式により算出できます。
| 電気代(円)=1回あたりの炊飯にかかる消費電力(Wh)÷1,000×1kWhあたりの電力量単価(円) |
たとえば、消費電力が200Whの炊飯器を使用した場合、1kWhあたりの電力量単価が31円とすると、1回あたりの電気代は約6円となります。
ただし、この金額はあくまで目安であり、炊飯するお米の量、季節による水温の違い、さらには室温といった外部環境によっても変動する可能性があります。
家庭の炊飯器の取扱説明書やカタログで消費電力を確認し、契約の電気料金プランと照らし合わせて計算してみることをおすすめします。
保温機能の電気代:つけっぱなしは損?
炊飯器の保温機能は便利ですが、電気代も気になるところです。
保温にかかる電気代は、次の計算式で算出できます。
| 電気代(円)=1時間あたりの保温にかかる消費電力(W)÷1,000×使用時間(h)×使用日数×1kWhあたりの電力量単価(円) |
1時間の保温にかかる消費電力が20Wh、電力量単価が31円と仮定すると、6時間保温した場合の電気代は約3.7円です。
保温にかかる電気代は、保温開始直後と一定時間が経過した後では消費電力が異なる場合があります。
一般的に、保温開始時はご飯の温度を維持するために比較的多くの電力を消費し、その後は安定した温度を保つために消費電力が下がります。
しかし、長時間保温を続けると、このわずかな電気代も積み重なり、結果として大きなコストになる可能性があります。
また、長時間の保温はご飯の風味を損ねたり、乾燥が進んだりするデメリットも考慮に入れる必要があるでしょう。
早炊き機能の電気代は通常炊飯と比べてどう違う?
多くの炊飯器に搭載されている早炊き機能は、忙しいときにご飯を短時間で炊き上げられる便利な機能です。
この早炊き機能を使用した場合の電気代は、通常炊飯と比べてどうなのでしょうか。
早炊き機能は、炊飯時間を短縮するために、一時的に通常炊飯よりも高い電力を使って加熱することがあります。
そのため、瞬間的な消費電力は大きくなる傾向にありますが、重要なのは炊飯1回あたりの総消費電力量 Whです。
機種によっては、炊飯時間が短い分、トータルの電力量で比較すると通常炊飯と大差ないか、むしろ少なくなるケースも見られます。
この点は炊飯器の機種やメーカーによって異なるため、使用の炊飯器の取扱説明書を確認するか、メーカーのWebサイトで情報を調べてみることをおすすめします。
1か月の炊飯器の電気代はどのくらい?試算してみよう
毎日使う炊飯器の電気代が1か月でどのくらいになるのか、具体的に試算してみましょう。
1か月の炊飯器の電気代は、1日あたりの炊飯回数、1回あたりの炊飯にかかる電気代、そして保温機能の使用時間によって大きく変わります。
たとえば、1回の炊飯で5円、1時間の保温で0.5円かかると仮定し、1日に2回炊飯して合計2時間保温する場合、1日あたりの電気代は(5円×2回)+(0.5円×2時間)=11円となります。
これを30日間続けると、1か月で330円です。
ただし、上記の金額はあくまで一例であり、家庭の家族構成やライフスタイル、使用する炊飯器の性能によって実際の金額は変動します。
自身の状況に合わせて計算し、家計管理の参考にしてみてください。
【比較】炊飯器の種類や使い方で電気代はこう変わる
炊飯器の電気代は、機種の種類や容量、さらには保温の仕方によっても差が出てきます。
IH式やマイコン式といった加熱方式の違い、3合炊きや5.5合炊きといった容量の違い、そして保温機能を使用するか冷凍保存して電子レンジで温めるかなど、さまざまな選択肢があります。
ここでは、これらの違いが電気代にどのように影響するのかを比較し、より経済的な炊飯器の使い方を探りましょう。
IH・マイコン・圧力IH:炊飯器の種類別電気代比較
炊飯器には主にIH炊飯器、マイコン炊飯器、そして圧力IH炊飯器という種類があります。
それぞれの電気代の目安は次のとおりです。
| 想定消費電力 | 1回あたりの炊飯電気代 | 6時間あたりの保温電気代 | 1か月(30日) あたりの電気代 | |
|---|---|---|---|---|
| IH炊飯器 | 炊飯:170Wh保温:15Wh | 約5.2円 | 約2.7円 | 約237円 |
| マイコン炊飯器 | 炊飯:160Wh保温:17Wh | 約4.9円 | 約3.1円 | 約240円 |
| 圧力IH炊飯器 | 炊飯:150Wh保温:16Wh | 約4.6円 | 約2.9円 | 約225円 |
※電気料金単価は31円/kWhで計算
近年の機種は省エネ性能も向上しており、一概にどの種類が最も電気代が高い、安いとはいえなくなってきています。
1か月あたりの電気代を比較しても大差はないため、炊き上がりの好みや予算と合わせて総合的に比較検討するとよいでしょう。
炊飯器の容量(3合、5.5合、一升炊き)による電気代の違い
炊飯器の容量も電気代に関係する要素の一つです。
一般的に、3合炊き、5.5合炊き、一升炊きといったように容量が大きい炊飯器ほど、一度に炊飯する際の消費電力が大きくなる傾向があります。
なぜなら、多くの量を炊くにはより大きなパワーが必要になるためです。
しかし、たとえば毎回1合しか炊かないのに一升炊きの炊飯器を使用するなど、炊く量に対して容量が大きすぎる炊飯器を使うのは効率的ではありません。
少量のご飯を大きな炊飯器で炊くよりも、適切な容量の炊飯器で必要な量を炊く方が、結果的に電気代を抑えられる場合があります。
家族の人数や一度に炊くご飯の量を考慮し、自身のライフスタイルに合った容量の炊飯器を選ぶことが、電気代の節約にもつながるといえるでしょう。
保温と冷凍+電子レンジ解凍のコスト比較:どっちがお得か
炊飯器でご飯を保温し続ける場合と、炊きあがったご飯を冷凍保存し、食べる際に電子レンジで解凍する場合とでは、どちらが電気代の面でお得なのでしょうか。
お茶碗一杯分の量と仮定した場合、電子レンジ(600W)で3分間ご飯を温めると、電気代は約0.93円です。
一方、1時間の保温にかかる消費電力が16Whの炊飯器の場合、電気代は約0.5円となります。
短時間、たとえば2〜3時間程度の保温であれば、炊飯器の保温機能を利用する方が手軽で電気代もそれほどかかりません。
しかし、6時間以上の長時間保温となると、保温にかかる電気代が積み重なり、冷凍保存して電子レンジで解凍する方が経済的になる傾向があります。
手間やご飯のおいしさも考慮に入れる必要がありますが、長時間保温することが多い場合は、冷凍保存という選択肢も検討してみる価値があるでしょう。
自身のライフスタイルや食事のタイミングに合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。
【実践】今日からできる!炊飯器の電気代を賢く節約する具体的な方法

炊飯器の電気代は、日々の小さな工夫で節約が可能です。
まとめ炊きをしたり、保温時間を見直したり、炊飯器の機能を上手に活用したりすることで、無理なく電気代を抑えられます。
ここでは、今日からすぐに実践できる炊飯器の電気代節約術を具体的に紹介します。
まとめ炊きで炊飯回数を減らす
炊飯器の電気代を節約する最も基本的な方法の一つは、まとめ炊きをして炊飯回数自体を減らすことです。
炊飯器は、お米を加熱して炊き上げる炊飯工程の開始時に最も多くの電力を消費します。
そのため、1日に何度も少量ずつ炊飯するよりも、2〜3食分など、ある程度の量を一度にまとめて炊く方が、トータルの消費電力を抑えられます。
まとめて炊いたご飯は、すぐに食べない分は小分けにして冷凍保存するなど、上手に保存方法を工夫することで、おいしさを保ちながら電気代の節約にもつながります。
週末にまとめて炊いておく、あるいは朝と夜の分を一度に炊くなど、自身の生活スタイルに合わせて取り入れてみてください。
保温時間は短く冷凍保存を上手に活用する
炊飯器の保温機能は便利ですが、長時間使用すると電気代がかさみます。
そのため、保温時間はできるだけ短くするよう心がけることが節約のポイントです。
ご飯が炊きあがったら、必要な分だけを取り分け、残りはすぐに食べる予定がなければ、保温し続けるのではなく、粗熱を取ってから小分けにして冷凍保存するのがおすすめです。
食べる際には電子レンジで温め直せば、炊きたてに近いおいしいご飯を味わえるうえ、長時間保温するよりも電気代を抑えられる可能性があります。
とくに数時間以上保温することが常態化している場合は、この方法に見直すことで、電気代の節約効果が期待できるでしょう。
エコモードやタイマー予約を賢く使う
最近の炊飯器の多くには、エコモードあるいは省エネモードといった、消費電力を抑えて炊飯する機能が搭載されています。
エコモードを活用すれば、通常炊飯時よりも電気代を少し抑えることが可能です。
具体的な削減効果は機種によって異なりますが、積極的に利用してみる価値はあるでしょう。
また、タイマー予約機能も電気代節約に役立ちます。食事の時間に合わせて炊きあがるようにタイマーをセットしておけば、炊飯後すぐに食べることができ、不必要な保温時間を減らすことができます。
朝食に炊きたてのご飯を食べたい場合や、帰宅時間に合わせて夕食の準備をしたい場合などに便利です。
これらの機能を上手に使いこなして、賢く電気代を節約しましょう。
省エネ性能の高い炊飯器を選ぶ
これから炊飯器の買い替えを検討している場合は、省エネ性能の高い機種を選ぶことが長期的な電気代の節約につながります。
炊飯器の省エネ性能を確認する際には、まず「省エネ基準達成率」や「年間消費電力量」といった指標をチェックしましょう。
これらの情報は、製品カタログやメーカーのWebサイト、家電量販店の店頭表示などで確認できます。
統一省エネラベルも参考になり、星の数が多いほど省エネ性能が高いことを示しています。
初期費用は多少高くても、年間を通して使用することを考えると、省エネ性能の高い炊飯器を選ぶことで、毎月の電気代を抑えられ、結果的にトータルのコストパフォーマンスがよくなる可能性があります。
意外と見落としがちかも?待機電力と内釜の手入れ
炊飯器の電気代を考えるうえで、意外と見落としがちなのが待機電力と内釜の手入れです。
炊飯器を使用していないときでも、コンセントにプラグが接続されている限り、わずかながら待機電力を消費しています。
待機電力は微量ですが、積み重なると無視できない金額になることもあります。
長期間家を空ける際や、普段あまり炊飯器を使わない場合は、コンセントからプラグを抜いておくことを検討してもよいでしょう。
また、内釜の汚れも熱効率を低下させる一因となり得ます。
内釜に焦げ付きや汚れが付着していると、熱が均一に伝わりにくくなり、余計な電力を消費する可能性があります。
内釜は使用後こまめに洗浄し、清潔な状態を保つことが、おいしいご飯を炊くのみでなく、電気代の節約にもつながるのです。
炊飯器の電気代をもっと抑えたいなら「電力会社のプラン見直し」が効果的!

炊飯器の使い方を工夫するのみでなく、家庭の電気料金プランそのものを見直すことで、電気代全体を大きく節約できる可能性があります。
2016年の電力自由化以降、消費者はライフスタイルに合わせて電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。
この機会に、自身の電気の使い方に最適なプランは何か、検討してみることをおすすめします。
電力自由化で選べるようになった電力会社とプラン
2016年4月から始まった電力の小売全面自由化により、それまで地域ごとに決められた大手電力会社としか契約できなかった一般家庭でも、自由に電力会社や料金プランを選べるようになりました。
この電力自由化を機に、多くの新しい電力会社、いわゆる「新電力」が市場に参入し、それぞれ特色のある多様な料金プランを提供しています。
たとえば、時間帯によって電気料金の単価が変わるプランや、ガスとセットで契約すると割引になるプラン、特定のサービスの利用でポイントが貯まるプランなど、選択肢は格段に広がりました。
自身のライフスタイルや価値観に合わせて、よりお得で魅力的な電力会社やプランを選択することが可能になったのです。
ライフスタイルに合った電力プランを選ぶメリット
電力会社や料金プランを見直す最大のメリットは、自身のライフスタイルに合ったプランを選ぶことで、電気代を効率的に削減できる可能性がある点です。
たとえば、日中は仕事や学校で家を空けていることが多く、主に夜間に電気を使用する家庭であれば、夜間の電気料金単価が割安に設定されているプランを選ぶことでメリットが得られるでしょう。
また、オール電化住宅に住んでいる方であれば、オール電化向けの専用プランが用意されている場合があります。
ほかにも、家族構成や趣味、環境への関心度など、さまざまな要素を考慮してプランを選択できます。
炊飯器のみでなく、家庭全体の電気の使い方を見つめ直し、最適な電力プランに切り替えることで、毎月の固定費である電気代を賢く節約することにつながるでしょう。
電力会社切り替えの簡単ステップと注意点
電力会社の切り替えは、多くの場合、インターネット上のWebサイトから簡単におこなえます。
新しい電力会社のWebサイトで申し込み手続きをおこない、必要事項を入力するのみです。
その際、現在契約している電力会社の検針票、つまり電気使用量のお知らせを手元に用意しておくと、契約者情報や供給地点特定番号などをスムーズに入力できます。
切り替えにかかる費用は原則として無料ですが、まれに契約期間の縛りや解約金が設定されているプランも存在するため、契約前には必ず詳細を確認することが重要です。
また、スマートメーターが未設置の場合は、新しい電力会社への切り替えに伴い、既存の電力計からスマートメーターへの交換工事がおこなわれることがあります。
この工事も原則無料でおこなわれます。
【自身に合ったプランは?】おすすめ電力サービス3選
| サービス | サービスの特徴 | 電気料金シミュレーション | おすすめな方 |
|---|---|---|---|
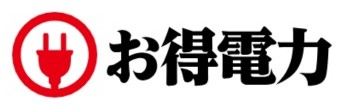 詳細を見る | ・大手電力会社からの乗り換えなら今のプランのまま電気代が確実に安くなる ・乗り換えはスマホで簡単・工事も不要 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ お得電力 従量電灯Bプラン 年間 約8,553円 お得! | ・手間やプラン変更なく電気代を安くしたい方 ・今の電力会社に不満はないが節約はしたい方 |
詳細を見る | ・電気の市場価格に合わせて料金が変動 ・使う時間を工夫すれば 電気代を大幅に節約可能 | 【例:4人家族の場合】 Loopでんき スマートタイムONE(電灯) 月額 約11,119円 ▼ 市場電力(電灯)プラン 年間 約3,180円 お得! | ・ゲーム感覚で積極的に節電を楽しみたい方 ・電気を使う時間を調整できるライフスタイルの方 |
 詳細を見る | ・契約するだけで 「のむシリカ」がもらえる ・電気を使えば使うほどもらえる特典が増量 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ のむシリカ電⼒ 従量電灯Bプラン 年間 約2,844円 お得! | ・電気代の節約と一緒に 健康にも気を配りたい方 ・毎月の電気使用量が 多い家庭 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まず
炊飯器の電気代節約術を実践するのみでなく、電力会社や料金プランを見直すことで、家計全体の電気代をさらに抑えられる可能性があります。
ここでは、それぞれの特徴を持つ3つの電力サービスを紹介します。
自身のライフスタイルや重視するポイントに合わせて、最適なプランを選んでみてください。
お得電力:大手電力会社の安心感はそのままに電気代を節約
「お得電力」は、現在大手電力会社と契約している方が、プラン内容を大きく変えることなく電気代を安くできるサービスです。
最大の魅力は、切り替え手続きが最短5分と非常に手軽な点です。
電力会社の切り替えがはじめてで不安な方や、複雑な手続きは避けたいけれど電気代は節約したいと考えている方におすすめです。
大手電力会社の供給エリアであれば、基本的にこれまでの電気の品質や安定性はそのままに、料金だけがお得になります。
まずは気軽に試してみたいという方に、強くおすすめできる選択肢の一つといえます。
市場電力:電気の使い方を工夫して大幅節約も
「市場電力」は、サービス料が低く設定されており、電気の卸売市場の価格に連動して電気料金が決まるプランが特徴です。
そのため、電気を使う時間帯を工夫することで、電気代を大幅に削減できる可能性があります。
たとえば、市場価格が安い時間帯に集中的に電気を使用したり、価格が高い時間帯の使用を控えたりなど、積極的な節電に取り組みたい方に向いています。
電力価格の変動を常に意識し、自身の生活スタイルを柔軟に調整できる方であれば、大きな節約効果が期待できるでしょう。
すでに新電力を利用しており、さらに踏み込んだ節約術を実践したいと考えている方にも、魅力的な選択肢となるはずです。
のむシリカ電力:嬉しい特典付きで毎日の暮らしをサポート
「のむシリカ電力」は、電気の契約に加えて、美容や健康に関心のある方に嬉しい特典が付いてくるユニークなサービスです。
契約時や毎月の電気料金に応じて、人気のミネラルウォーター「のむシリカ」がプレゼントされる点が大きな特徴です。
また、オール電化向けの料金プランも選べるため(一部非対応地域あり)、とくに電力使用量が多い家庭にとっては、電気代の節約と合わせて魅力的な特典を受けられる可能性があります。
電気という日々の生活に不可欠なインフラに、プラスアルファの価値や楽しみを求めたい方、健康志向の方にとっては、検討する価値のある電力サービスといえるでしょう。
炊飯器の電気代に関するよくある質問

炊飯器の電気代について、さらに詳しく知りたい方のために、よくある質問とその回答をまとめました。
炊飯器の寿命やガス炊飯器との比較、最新機種の省エネ効果など、気になる疑問を解消しましょう。
炊飯器の寿命は電気代に影響しますか?
一般的に、家電製品は長年の使用による経年劣化で、内部の部品の効率が少しずつ低下し、結果として購入当初よりも消費電力が若干増加する可能性は否定できません。
ただし、それが毎月の電気代に目に見えて大きな影響を与えるほどになるかどうかは、炊飯器の機種や使用状況、メンテナンスの状態によって大きく異なります。
たとえば、内釜のコーティングが剥がれて熱効率が悪くなったり、温度センサーの精度が落ちたりすると、余計な電力消費につながることも考えられます。
もし、炊飯器の調子が明らかに悪い、炊き上がりにムラがある、あるいは以前よりも電気代が高くなったように感じるなどの場合は、点検や修理、または省エネ性能の高い新しい機種への買い替えを検討するのも一つの選択肢といえるでしょう。
ガス炊飯器と電気炊飯器は光熱費で比較するとどちらが安いですか?
ガス炊飯器と電気炊飯器の光熱費を比較する場合、一概にどちらが安いといい切るのは難しいのが現状です。
ガス炊飯器は、一般的に短時間で高火力で炊き上げるため、1回あたりの炊飯にかかる光熱費は電気炊飯器よりも安い傾向があるといわれています。
しかし、ガスには都市ガスとプロパンガスがあり、それぞれの基本料金や単価が異なります。
また、電気料金も契約している電力会社や料金プランによって単価が変動します。
そのため、単純な炊飯時のコストのみでなく、家庭で契約しているガスの種類や料金、電気の契約内容を総合的に考慮して比較する必要があります。
さらに、炊飯器本体の価格や設置場所の制約(ガス栓の有無など)も選択の際の重要なポイントとなるでしょう。
最新の炊飯器は本当に省エネ効果が高いのですか?
近年の炊飯器は省エネ技術が大きく進歩しており、数年前の古い機種と比較すると、年間消費電力量が大幅に削減されているものが多く見られます。
とくに、インバーター制御によって加熱を細かくコントロールする技術や、内釜の素材や構造の改良による熱効率の向上、あるいは真空技術を利用して保温時の消費電力を抑えるといった工夫が凝らされています。
これにより、おいしさを追求しながらも、十分に省エネ性能を高めている機種が増えています。
炊飯器の買い替えを検討する際には、製品カタログや店頭表示で「省エネ基準達成率」や「年間消費電力量」といった指標を確認し、最新機種の省エネ効果をチェックしてみることをおすすめします。
長期的な視点で見れば、初期費用が多少高くても、日々の電気代を抑えられる省エネ性能の高い炊飯器を選ぶメリットは大きいといえるでしょう。
まとめ:炊飯器の電気代を理解し賢い選択で家計にゆとりを!
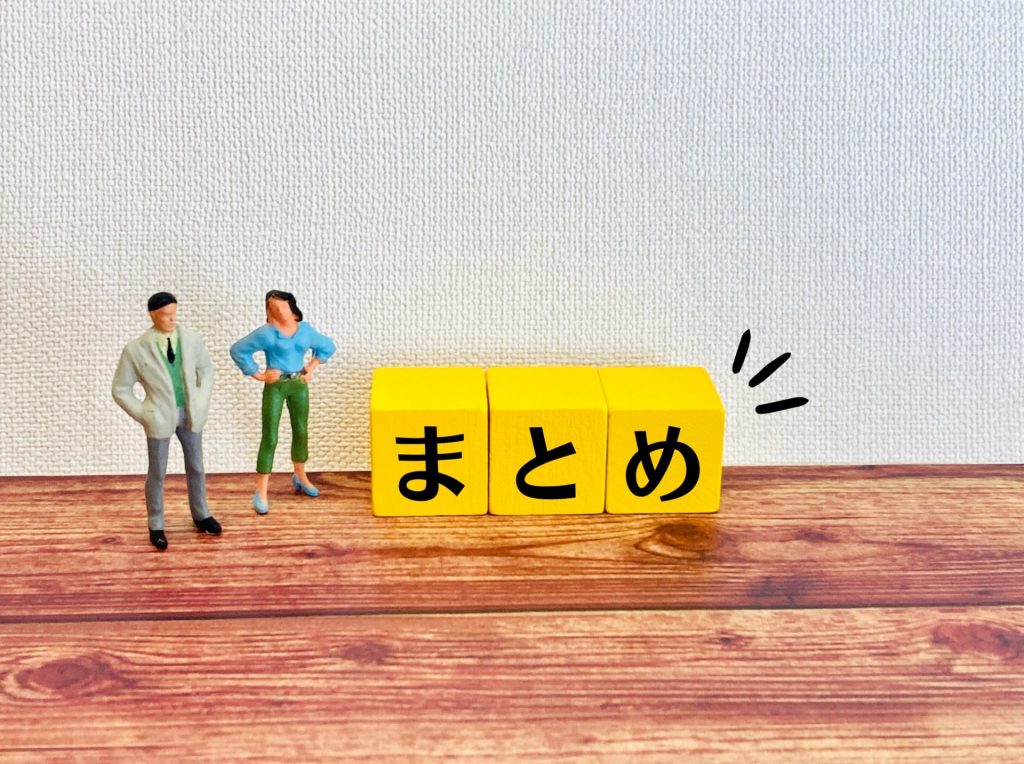
本記事では、炊飯器の電気代について、1回あたりのコストから保温や早炊き機能使用時の比較、1か月の目安、そして具体的な節約術まで詳しく解説しました。
炊飯器の電気代は、使い方や機種によって変動しますが、日々の小さな工夫や、省エネ性能の高い製品を選ぶことで、着実に節約効果が期待できます。
さらに、自身のライフスタイルに合った電力プランを選択すれば、家庭全体の電気代をより効果的に抑えることが可能です。
今回紹介した「お得電力」「市場電力」「のむシリカ電力」といった電力サービスも参考に、炊飯器の使い方と合わせて、ぜひ家庭の電気代全体の見直しを検討してみてください。