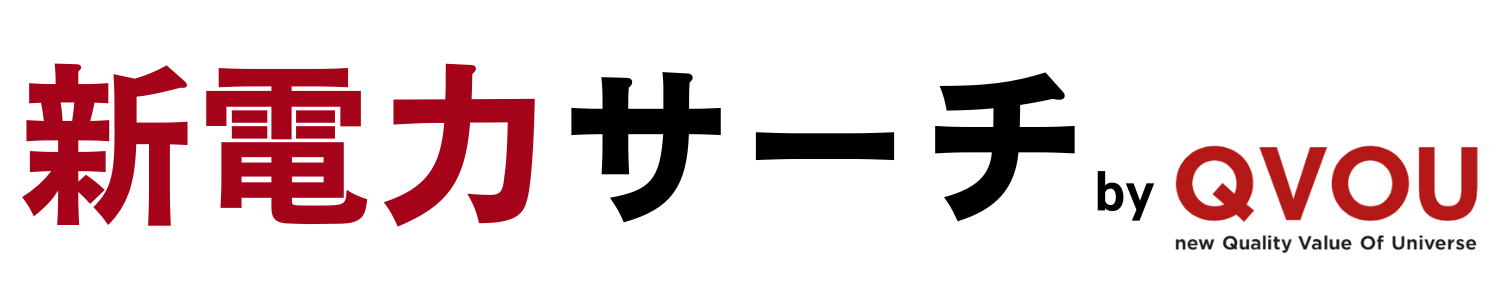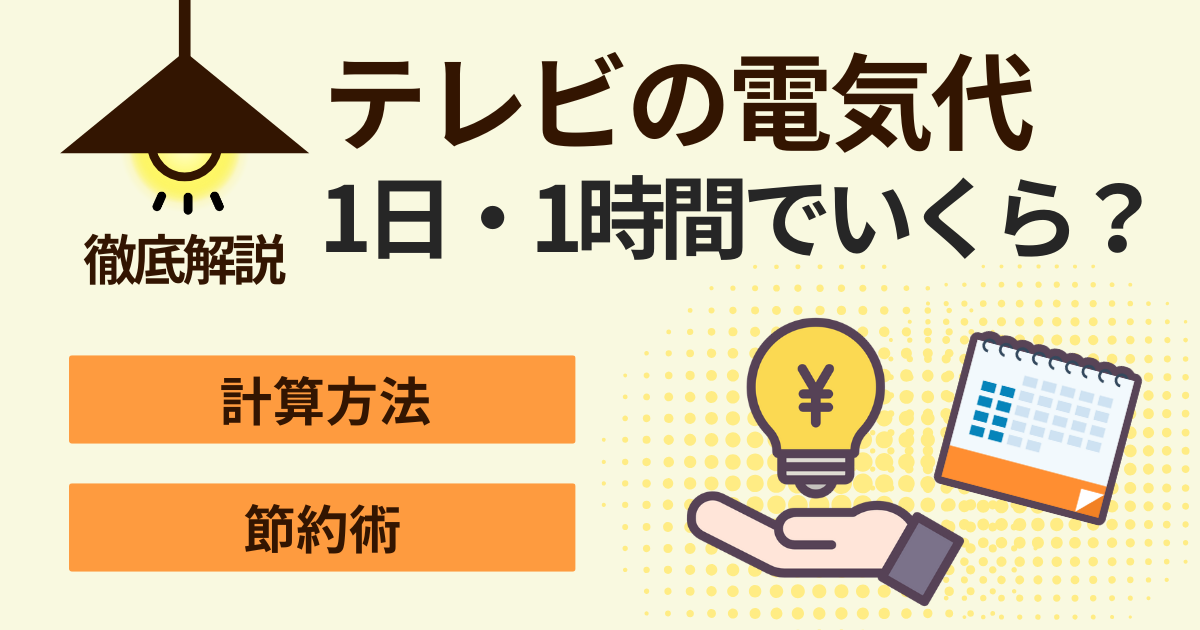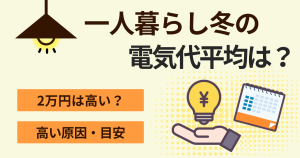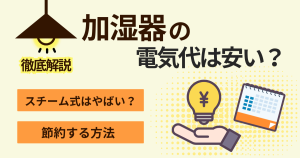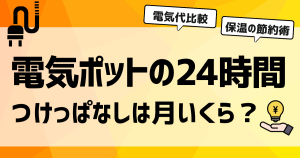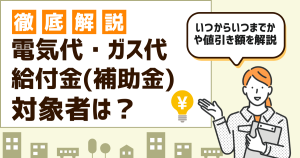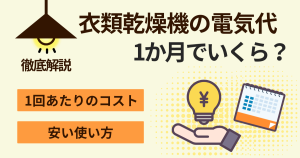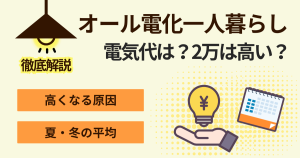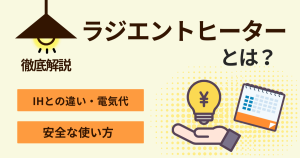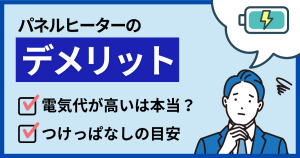テレビは多くの家庭にとって、生活に欠かせない身近な家電です。
しかし、毎日視聴する中で電気代は1日あたり、1時間あたりで一体いくらかかっているのか、テレビをつけっぱなしにすると家計にどれくらい影響するのかといった疑問を持つ方も少なくありません。
結論として、テレビの電気代は自身で計算すれば把握可能であり、日々の工夫と根本的な対策によって効果的に節約できます。
本記事では、テレビの電気代の具体的な計算方法から、サイズや種類による料金の違い、今日から実践できる節約術をわかりやすく解説します。
電気代への漠然とした不安を解消したい方、本質的な家計改善を目指す方はぜひ参考にしてください。
| サービス | サービスの特徴 | 電気料金シミュレーション | おすすめな方 |
|---|---|---|---|
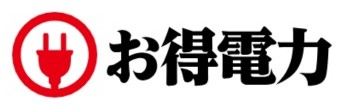 詳細を見る | ・大手電力会社からの乗り換えなら今のプランのまま電気代が確実に安くなる ・乗り換えはスマホで簡単・工事も不要 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ お得電力 従量電灯Bプラン 年間 約8,553円 お得! | ・手間やプラン変更なく電気代を安くしたい方 ・今の電力会社に不満はないが節約はしたい方 |
詳細を見る | ・電気の市場価格に合わせて料金が変動 ・使う時間を工夫すれば 電気代を大幅に節約可能 | 【例:4人家族の場合】 Loopでんき スマートタイムONE(電灯) 月額 約11,119円 ▼ 市場電力(電灯)プラン 年間 約3,180円 お得! | ・ゲーム感覚で積極的に節電を楽しみたい方 ・電気を使う時間を調整できるライフスタイルの方 |
 詳細を見る | ・契約するだけで 「のむシリカ」がもらえる ・電気を使えば使うほどもらえる特典が増量 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ のむシリカ電⼒ 従量電灯Bプラン 年間 約2,844円 お得! | ・電気代の節約と一緒に 健康にも気を配りたい方 ・毎月の電気使用量が 多い家庭 |
※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まず
【結論】テレビの電気代は1時間あたり約0.5円から!計算方法と料金の仕組みを解説

家庭にあるテレビの電気代は、簡単な計算式で算出できます。
ここからは、テレビの電気代を把握するために必要な次の3つのポイントを解説します。
- テレビの電気代を自身で計算する簡単な計算式
- 計算に必要な消費電力(W・kW)の確認方法
- 電気料金単価の目安とその内訳
それぞれの内容を具体的に解説します。
テレビの電気代を求める計算式
テレビの電気代は、消費電力と使用時間、そして電気料金単価がわかれば簡単に計算できます。
具体的な計算式は次のとおりです。
計算式
消費電力(kW)× 使用時間(h)× 電気料金単価(円/kWh)
ここで注意したいのが、消費電力の単位です。
テレビ本体やカタログに記載されている消費電力は「W」(ワット)で表記されていることが大半ですが、計算式では「kW」(キロワット)を使用します。
WからkWへの変換は、数値を1000で割ることで求められます。
たとえば、消費電力が100Wのテレビであれば、0.1kWとして計算します。
計算に必要な消費電力の確認方法
電気代の計算に必要となるテレビの消費電力は、いくつかの方法で確認が可能です。
最も簡単な方法は、テレビ本体の背面や側面に貼られているシールや、付属の取扱説明書を見ることです。
多くの場合「定格消費電力」としてW(ワット)単位で記載されています。
また、より実際の使用状況に近い目安として「年間消費電力量」を確認するのもよいでしょう。
これは省エネ法に基づき、一般家庭の平均的な使用状況(1日の視聴時間や待機時間など)を想定して算出された数値で、kWh/年という単位で記載されています。
各メーカーの公式サイトに掲載されている製品のスペック表からも、これらの数値を確認できます。
電気料金単価の目安
電気料金単価とは、電気を1kWh使用したときにかかる料金のことです。
この単価は、契約中の電力会社や料金プランによって異なります。
正確な単価は家庭の検針票などで確認するのが確実ですが、自身で計算する際の目安として、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が定める「31円/kWh」(税込)を使用するとよいでしょう。
また、私たちが支払う電気料金は、電力量料金のほかに、毎月固定でかかる基本料金や、燃料費の変動を調整する燃料費調整額、再生可能エネルギーの普及を目的とした再エネ賦課金などで構成されています。
こうした仕組みを理解しておくと、電気代への関心もより深まるでしょう。
出典:よくある質問 Q&A|公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会
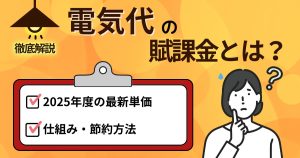
【条件別】テレビの電気代比較 サイズ・種類・使用年数でどう変わるか

テレビの電気代は、使用しているテレビのスペックによって大きく変わります。
とくに、画面の大きさやパネルの種類、そして製造された年式は、電気代を左右する重要な要素です。
まずは、一般的な40型液晶テレビ(消費電力80Wと仮定)をモデルケースとして、利用時間ごとの電気代がいくらになるか解説します。
| 視聴時間 | 電気代(1日あたり) | 電気代(30日あたり) |
|---|---|---|
| 1時間 | 約2.5円 | 約75円 |
| 8時間 | 約19.8円 | 約595円 |
| 24時間 | 約59.5円 | 約1,786円 |
つけっぱなしにすると月々2,000円近い出費になる可能性があり、視聴時間の管理が重要であることがわかります。
ここからは、さらに詳しく次の4つの条件で電気代がどれくらい違うのかを比較します。
- テレビの画面サイズによる電気代の違い
- パネルの種類(液晶・有機EL)による電気代の比較
- 最新モデルと10年前のモデルの電気代比較
- 省エネ性能の高いテレビの選び方
自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてください。
画面サイズ別の電気代比較
テレビの電気代は、画面サイズが大きくなるほど高くなる傾向があります。
画面が大きいテレビは、表示のためにより多くの電力が必要になるためです。
32型、40型、55型、65型といった代表的なサイズで、1時間あたりの電気代を比較すると、その差がよくわかります。
| 画面サイズ | 想定消費電力 | 1時間あたりの電気代 |
|---|---|---|
| 32型 | 60W | 約1.9円 |
| 40型 | 80W | 約2.5円 |
| 55型 | 100W | 約3.1円 |
| 65型 | 130W | 約4円 |
もちろん機種によって消費電力は異なりますが、一般的には大型になるにつれて電気代は着実に増加します。
また、近年主流となっている4Kや8Kといった高画質のテレビは、映像をより緻密に表現するために多くの画素を動かす必要があり、同じサイズのフルハイビジョンテレビと比較して消費電力が大きくなる可能性があります。
液晶と有機ELテレビの電気代比較
現在販売されている薄型テレビのパネルは、主に液晶と有機ELの2種類に分けられます。
この2つは映像を表示する仕組みが異なり、電気代にも違いが生まれます。
液晶テレビは、バックライトと呼ばれる光源で画面全体を照らし、液晶シャッターで光の量を調整して映像を映し出す仕組みです。
一方、有機ELテレビは画素の一つひとつが自ら発光するため、バックライトが必要ありません。
同じサイズの最新モデルで比較した場合、一般的には有機ELテレビの方が液晶テレビよりも消費電力が少なく、電気代が安くなる傾向にあります。
とくに、黒色を表現する際に有機ELは画素の発光をオフにするため、消費電力を大幅に抑えられる点が特長です。
最新モデルと10年前のテレビで電気代はどれくらい違うか
テレビの省エネ技術は年々向上しており、最新モデルは古いモデルと比較して消費電力が大幅に抑えられています。
次の表は、2020年と2010年のテレビの年間消費電力を比較したものです。
| 画面サイズ | 2020年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 24V型 | 43.7kWh/年 | 83kWh/年 |
| 32V型 | 56.4kWh/年 | 93kWh/年 |
| 42V型 | 106kWh/年 | 162kWh/年 |
| 55V型 | 155kWh/年 | 318kWh/年 |
出典:省エネ性能カタログ2010年版
32V型テレビの場合、電気代を電気料金単価31円/kWhとして計算すると、2010年は年間約2,883円なのに対し、2020年には年間約1,748円となります。
もし家庭で10年以上前のテレビ、とくにプラズマテレビなどを使用している場合、最新の省エネモデルに買い替えることで、電気代に大きな差が生まれる可能性があります。
テレビ本体の購入費用はかかりますが、長期的に見れば毎月の電気代削減によって、買い替えが結果的に大きな節約につながることもあるため、ぜひ検討してみてください。
省エネ性能の高いテレビの選び方
テレビの買い替えを検討する際には、省エネ性能に注目して選ぶことが大切です。
家電量販店や通販サイトでは、「省エネ基準達成率」という指標を確認しましょう。
これは、国が定めた省エネ基準をどれくらい達成しているかを示すもので、パーセンテージが高いほど省エネ性能が高いことを意味します。
また、製品スペックに記載されている「年間消費電力量(kWh/年)」の数値も重要な比較ポイントです。
同じインチサイズのテレビであれば、この数値が小さいほど年間の電気代が安くなります。
これらの指標を参考に、長期的なコストを意識して製品を選ぶことをおすすめします。
今日からできるテレビの電気代節約術9選!すぐに効果が出る方法

テレビの電気代は、日々の少しの工夫で着実に節約できます。
ここでは、効果的な節約術を次の3つのカテゴリーに分けて9つ紹介します。
- 画面の明るさや設定の見直しによる節約
- 使い方を工夫するだけの簡単節約術
- 意外と見落としがちな待機電力の削減
自身のライフスタイルに合わせて、取り入れやすいものから試してみてください。
画面の明るさ調整と省エネモードの活用
テレビの消費電力で大きな割合を占めるのが、画面のバックライトです。
たとえば32V型の液晶テレビの場合、画面の明るさを最大から中間にするのみで、年間で約730円もの節約になります。
また多くのテレビには、部屋の明るさに応じて画面の輝度を自動で調整してくれる「明るさセンサー」や、消費電力を全体的に抑える「省エネモード」といった機能が搭載されています。
これらの設定をオンにしておくのみで、意識せずとも無駄な電力消費を削減できるでしょう。
また、必要以上に音量を大きくすることも電力の消費につながります。
適切な音量に調整することも、ささやかですが大切な節約術の一つです。
無駄な視聴をなくし主電源をオフにする習慣
何となくテレビをつけておく「ながら見」や、誰も見ていないのに流しっぱなしにする習慣をなくしましょう。
こうした無駄な視聴時間をなくし、見ていないときはこまめに電源をオフにすることが節約の基本です。
最近のテレビには、一定時間操作がないと自動で電源が切れる「無操作電源オフ機能」が搭載されていることが多くあります。
この機能を設定しておけば、消し忘れた際にも安心です。
また、就寝前や長時間の外出時には、リモコンで電源を切るのみでなく、テレビ本体の主電源をオフにする習慣をつけると、より着実に節約ができます。
使わないときはコンセントを抜いて待機電力をカット
テレビは、リモコンで電源をオフにした状態でも、番組表の受信やシステムのアップデートのために微量の電力を消費しています。
この電力を待機電力と呼び、電気代はそれほど大きくはありませんが、ゼロではないことも事実です。
旅行や帰省などで長期間テレビを使用しない場合は、コンセントからプラグを抜くことで、待機電力を完全にカットできます。
毎回コンセントを抜き差しするのが面倒な場合は、スイッチ付きの電源タップを活用するのもおすすめです。
手元のスイッチ一つで電源を完全にオフにできるため、手軽に待機電力の節約を実践できます。
【本質的な節約】テレビ本体の節約だけでは不十分?電気代の根本的な見直し

テレビ本体の設定や使い方を工夫する節約術は手軽で重要ですが、電気代が大幅に安くなるとは限りません。
より大きな節約効果を求めるなら、電気代の請求額そのものを決めている根本的な部分、つまり電気の契約プランに見直しの目を向けることが不可欠です。
この章では、本質的な電気代節約のために知っておきたい次の3つのポイントを解説します。
- テレビの省エネ性能向上と電気料金の値上がりという現実
- 電気代の大部分を占める料金単価の重要性
- 電力自由化で可能になった電力会社の乗り換えという選択肢
なぜ電力会社の契約見直しが重要なのか、その理由を詳しく解説します。
節約術を実践しても電気代が下がらない理由
テレビの省エネ性能は向上しているのに、なぜか電気代は安くならないと感じる方もいるでしょう。
その主な原因は、電気そのものの料金単価が上昇傾向にあるためです。
近年、世界的な燃料価格の高騰などの影響を受け、多くの電力会社で電気料金が値上がりしています。
そのため、テレビ本体の消費電力が減っても、電気を作るためのコストが上がっていることで、最終的な請求額が下がりにくい状況が生まれています。
使い方を工夫する節約術の効果には限界があり、それだけでは料金単価の上昇分を吸収しきれない可能性があるのです。
電気代の基本は契約プランの料金単価で決まる
毎月の電気代の請求額は、主に毎月固定でかかる「基本料金」と、電気の使用量に応じて決まる「電力量料金」の合計で構成されています。
このうち、電気を使用すればするほど増える電力量料金を決めているのが「料金単価」です。
この料金単価は、実はどこの電力会社でも同じというわけではありません。
現在契約している電力会社や料金プランによって、1kWhあたりの単価は大きく異なります。
つまり、同じ量の電気を使用しても、契約先が違うだけで支払う金額に差が生まれるという仕組みです。
そのため、料金単価の安いプランを選ぶことが、電気代節約のコツです。
最も効果的な節約方法は電力会社の乗り換え
現在、私たちが契約する電力会社は、自由に選択できます。
これは、2016年4月にはじまった「電力自由化」により、それまで地域ごとに決められていた電力会社以外にも、さまざまな事業者が電気の販売に参入できるようになったためです。
経済産業省 資源エネルギー庁の資料によると、電力自由化以降、数多くの新電力事業者が誕生し、多くの家庭が自身のライフスタイルに合った電力会社への乗り換えを選択しています。
もし現在、地域の大手電力会社と契約しているのであれば、より料金単価の安い新電力に乗り換えることが、最も効果の大きい根本的な節約方法といえるでしょう。
乗り換えても送られてくる電気の品質や安全性は変わらないうえ、手続きもWebサイトで完結する場合が大半です。
テレビの視聴スタイルに合わせたおすすめ新電力3選
| ライフスタイル |
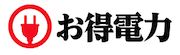
|

|
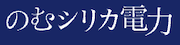
|
|---|---|---|---|
|
ケース1 共働きで 日中不在がち |
\節約期待度/
生活を変えず、確実に節約したい家庭に最適。シンプルに料金が安くなるのが最大のメリットです。 |
\節約期待度/
日中不在時は恩恵が少なめ。電気をよく使う朝晩・休日の価格高騰リスクに注意が必要です。 |
\節約期待度/
大手より安い料金+「のむシリカ」特典が魅力。標準的な使用量でもお得感をプラスできます。 |
|
ケース2 在宅ワーク中心で 昼間によく使う |
\節約期待度/
確実に安くなる安心感が魅力。大きな節約より、安定した割引を求める方におすすめです。 |
\節約期待度/
市場価格が安い昼間に電気を使えるため、電気代を大幅に削減できる可能性が最も高いプランです。 |
\節約期待度/
電気使用量が多い家庭に最適。「のむシリカ」特典を多く受け取れるため、料金+特典でお得です。 |
|
ケース3 家族が多く 電気使用量が多い |
\節約期待度/
使用量が多いほど削減額もアップ。シンプルに電気代を安くしたい家庭に最適です。 |
\節約期待度/
使用量が多いため、市場価格高騰時のリスクが大。時間帯を気にせず使う家庭には不向きです。 |
\節約期待度/
電気料金に応じて「のむシリカ」特典。電気使用量が最も多い家庭で、特典価値が最大になります。 |
電力会社の見直しが最も効果的な節約方法であると理解できても、数多くある新電力の中からどれを選べばよいか迷う方もいるでしょう。
ここでは、テレビの視聴スタイルや電気に対する価値観に合わせて、特徴の異なる3つの新電力サービスを紹介します。
- とにかくシンプルに安くしたい方向けのお得電力
- 日中のテレビ視聴が多い方向けの市場電力
- 電気代を付加価値に変えたい方向けののむシリカ電力
それぞれのサービスが、どのような方におすすめなのかを具体的に解説します。
①手間なく確実に安くしたいならお得電力
「難しいことは考えず、とにかくシンプルに電気代を安くしたい」という方には、お得電力がおすすめです。
お得電力は、東京電力など各地域の大手電力会社が提供する一般的な料金プランと比較して、基本料金と電力量料金単価が安く設定されていることが最大の魅力です。
そのため、テレビの視聴時間やライフスタイルを変えることなく、大手電力会社から乗り換えるのみで、毎月の電気代が安くなります。
運営会社である株式会社Qvouは、2025年時点で創業40年近い歴史を持つ総合企業であり、安心して契約できる点も魅力です。
「まずは着実に電気代を削減したい」と考える方に適しています。
②日中のテレビ視聴が多いなら市場電力
「在宅勤務などで日中にテレビを見ることが多い」「電気を使う時間を工夫して、積極的に節約を楽しみたい」という方には、市場電力が向いています。
市場電力は、電気の取引価格である市場価格に連動して、30分ごとに電気の料金単価が変動する「市場連動型プラン」です。
太陽光発電の量が増える晴れた日の昼間などは、市場価格が安くなる傾向があります。
そのため、料金が安い時間帯にテレビを見たり、家事を済ませたりといった「ピークシフト」を意識することで、電気代を大きく抑えられる可能性があります。
自身の工夫次第で節約効果が大きくなる、主体的に電気代を管理したい方に適したプランです。
③電気代にプラスアルファの価値を求めるならのむシリカ電力
「電気代の節約はもちろん、何か嬉しい特典があるとさらに満足できる」という方は、のむシリカ電力を検討してみてください。
のむシリカ電力は、電気を契約すると、霧島天然水「のむシリカ」が特典としてもらえるユニークなサービスです。
新規契約時にはもれなく1箱がプレゼントされるほか、1年間の電気料金に応じて、契約更新時にも使った分だけ「のむシリカ」がもらえます。
テレビを長時間見て電気代が多くなっても、その分特典が増えると考えれば、毎日のテレビ視聴がより楽しいものになるでしょう。
「電気代を暮らしを豊かにする価値に変えたい」と考える方に適しています。
テレビの電気代に関するQ&A

ここでは、テレビの電気代に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。
さまざまな疑問を解消し、テレビの電気代に関する不安をなくしましょう。
つけっぱなしとこまめに消すのはどちらがお得か
見ていないときは「こまめに消す」方が電気代の節約につながります。
一昔前のブラウン管テレビなどでは、電源を入れる瞬間に大きな電力を消費するため「つけっぱなしの方がお得」といわれることもありました。
しかし、現在の液晶テレビや有機ELテレビは起動時の消費電力が格段に抑えられているため、見ていない時間があれば、その都度消す方がお得です。
少なくとも30分以上テレビを見ない場合は、電源をオフにする習慣にするとよいでしょう。
テレビの待機電力は1か月でいくらくらいか
テレビが消費する待機電力は、機種や年式によって異なりますが、それほど大きな金額にはなりません。
近年の省エネ性能が高いモデルであれば、1か月あたりの待機電力による電気代は、数円から数十円程度が目安です。
ただし、待機電力を消費する家電はテレビのみではありません。
DVDレコーダーやオーディオ機器、インターネットのルーターなど、家庭内にあるさまざまな機器の待機電力が積み重なると、無視できない金額になる可能性があります。
テレビ単体では小さくとも、家全体で待機電力を意識することが大切です。
テレビとエアコンで電気代が高いのはどちらか
一般的に、家庭内の家電製品の中で比較すると「エアコン」の方がテレビよりも電気代は高くなる傾向にあります。
エアコンは、部屋の温度を調整するためにモーターやコンプレッサーを動かすため、映像を表示するのみのテレビよりも大きな電力を必要とすることが特徴です。
とくに、冷房や暖房を長時間使用する夏や冬は、エアコンの電気代が家計の中で大きな割合を占めることが多くあります。
経済産業省 資源エネルギー庁の調査でも、家庭における家電製品の電力消費割合は、エアコンが上位に挙げられています。
テレビの電気代も大切ですが、家計全体を見直す際は、まずエアコンの使い方から見直してみるのが効果的です。
まとめ

本記事では、テレビの電気代の計算方法、サイズや種類による料金の違い、そして具体的な節約術について解説しました。
テレビ本体の設定や使い方を見直すことも大切ですが、最も効果的な節約方法は、自身のライフスタイルに合った電力会社のプランへ乗り換えることです。
電気料金の仕組みは複雑に感じる部分もありますが、本記事で解説した情報を参考に、家庭にとって最適な選択を検討してみてください。
より詳細な情報は各サービスの公式サイトで確認するか、サービス名「お得電力」「市場電力」「のむシリカ電力」で検索することをおすすめします。